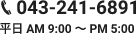機密文書は企業の経営や競争力に直結する重要な情報を含むため、漏洩リスクを防ぐための対策が必須です。本記事では、機密文書の重要度についてやそれぞれのレベルに適した管理・保管方法を詳しく解説します。

書類保管サービス「書庫番人」でコスト削減
機密文書とは?
機密文書とは、企業にとって極めて重要な書類やデータを指します。万が一、情報が外部に流出すると、企業に甚大な損害や損失をもたらす可能性があります。例えば、競争相手に戦略情報が渡ってしまったり、顧客情報が流出することで企業の信頼が損なわれたりするリスクを含んでいます。競争優位性を守るためにも、機密文書は慎重に取り扱いましょう。
機密文書のレベルは3つに分類される
機密文書は、その重要度によって「極秘文書」「秘文書」「社外秘文書」の3つに分類されます。また、機密文書以外には、特に機密性が求められない一般書類も存在します。機密性のレベルに応じて管理基準を設けることで、情報を適切に保護できるでしょう。

| 書類の種類 | 書類の内容の例 | 機密性と理由 | 主な管理基準 |
|---|---|---|---|
| 極秘文書 | 企業の財務情報・経理情報、新製品設計図、研究データ、顧客管理情報など | 極めて高い:漏洩すれば競争力に大打撃を与え、損害が甚大なため | 上層部のみ閲覧可、厳重なアクセス制限 |
| 秘文書 | 重要契約書、規程、製品販売情報、コスト情報、人事ファイルなど | 高い:情報漏洩により利益や競争優位性が損なわれる可能性があるため | 特定の管理者のみアクセス権制限 |
| 社外秘文書 | 会議議事録、顧客リスト、企画書、見積書など | 中程度:外部流出で信頼を損ない、競合他社に利用されるリスクがあるため | 社内でのみ共有、外部非公開 |
| 公開書類・一般書類 | パンフレット、カタログ、社内誌、営業日誌など | 低い:公開しても企業に与える影響がほとんどないため | 管理の厳重さは求められない |
極秘文書
極秘文書は、機密文書の中でも最も厳しい管理が求められる書類です。これらの書類には、企業の経営に直接関わる重要な情報が含まれています。万が一漏えいが発生すると、企業に大きな損害をもたらすだけでなく、信頼を失う可能性もあります。そのため、取り扱いには厳密なアクセス制限を設けて、関係者以外が閲覧できない仕組みを整えるべきといえます。
保管場所についても、専用の保管室や鍵付き保管庫を用意し、関係者以外が立ち入れない仕組みを設けることが理想的です。極秘文書が電子データの場合には、暗号化やアクセスログの記録といったセキュリティ対策を徹底する必要があります。
秘文書
秘文書は、極秘文書ほどの厳重な管理が求められるわけではありませんが、企業活動において重要な情報を含む書類です。これらの書類は特定の部門やプロジェクトチーム内で共有されることが多く、情報漏えいが起きると企業に重大な不利益をもたらす可能性があります。
秘文書の管理では、アクセス権を制限し、特定の責任者が管理を行うことが基本です。書類の保管には、鍵付きの保管庫や限定されたスペースを利用し、定期的に所在確認を行い、適切な管理を徹底すべきでしょう。また、社内での共有範囲を最小限に抑えることも重要です。このような対策により、情報漏えいのリスクを軽減できます。
社外秘文書
社外秘文書は、社内で共有することを前提とした書類で、情報の外部漏洩を防ぐために一定の管理体制が必要です。このカテゴリーの書類が社外に流出すると、企業の信頼やブランド価値が損なわれる可能性があるため、慎重に扱う必要があります。
社外秘文書の保管には、鍵付きキャビネットやセキュリティ設定が施されたデジタル保管システムが適しています。特に、社外へ持ち出す場合は、管理者の許可を得る仕組みを導入し、不用意な持ち出しや第三者に見られるリスクを排除する仕組みを導入するとよいでしょう。
レベル別の機密文書の保管方法
機密文書の保管方法は、その重要度(レベル)に応じて明確に区分し、それぞれに適した管理方法を適用する必要があります。
基本的な管理の流れ
全社的に書類の分類基準を設定し、どの書類が「極秘文書」「秘文書」「社外秘文書」に該当するのかを明確にすることが第一歩となります。これは企業によって異なるため、機密文書管理規定を設ける必要があります。分類基準が曖昧な場合、管理体制全体が不安定となり、情報漏えいのリスクが高まるため注意しましょう。
機密文書管理マニュアルの整備と社内周知
機密文書の適切な保管には、明確な管理マニュアルの存在が不可欠です。このマニュアルには、書類の分類基準、保管場所の指定、閲覧権限の範囲、管理者の責任範囲などが詳細に記載されている必要があります。さらに、全社員に対してこのマニュアルを周知し、内容を確実に理解させることが大切です。定期的にマニュアルの内容を見直し、最新の状態を維持していきましょう。
閲覧権限と責任者の明確化
機密文書を保管する際には、閲覧権限を明確にし、責任者を明示することが欠かせません。機密文書のレベル(極秘文書、秘文書、社外秘文書)ごとに、誰が閲覧可能で、誰が管理責任を負うのかを明確に定める必要があります。例えば、極秘文書は経営層やプロジェクトリーダーなど、厳しく限定された人のみが閲覧できるようにします。一方、秘文書や社外秘文書では、部署内やチーム内で閲覧範囲を広げる場合があります。責任者を明確にすることで、書類の所在確認や定期点検がスムーズになり、万が一、情報漏えいが発生した際にも迅速な対応が可能になります。このように、閲覧権限と責任者を定めることで、全体の管理精度を高められるでしょう。
保管場所の選定と管理体制
保管場所は、機密文書のレベルに応じて適切に選定する必要があります。極秘文書は、専用の保管室や鍵付き金庫など、高いセキュリティが確保された場所に保管します。さらに、監視カメラやアクセスログの記録といった追加の安全措置を導入することが推奨されます。秘文書や社外秘文書の場合、必要に応じてアクセスしやすい保管場所を選ぶとよいです。頻繁に利用する書類であれば、簡単に取り出せる保管庫やキャビネットを使用することで、利便性を高めつつ不要なリスクを抑えられます。また、保管スペースが限られている場合には、専門の書類保管サービスを活用するとより効率的に管理できます。書類の特性や利用頻度に応じた保管体制を整えていきましょう。
定期的な管理と見直しの必要性
機密文書の管理体制は、一度設定すれば完了というものではなく、定期的に見直しを行い、必要に応じて改善することが重要です。中でも、書類の保管期間を確認し、古い書類が不要であれば適切に整理や廃棄を行う必要があります。また、保管場所や管理体制が最新の状況やセキュリティ要件に対応しているかどうかを定期的に確認し、不足があれば速やかに補強するとよいでしょう。さらに、社員への教育も欠かせません。機密文書の取り扱いルールを定期的に全社員へ共有し、実務に反映させることで、人為的ミスによる情報漏えいのリスクを低減できるでしょう。
機密文書をレベル別に保管するコツ
機密文書を適切に保管するためには、重要度(レベル)に応じて分類し、保管場所や管理方法を明確にしましょう。まず、社内で「機密文書一覧表」を作成し、書類の種類、保管期間、保管場所、機密レベルを記録します。この一覧表を作成することで、どの書類がどこにあり、どのように管理されているかを簡単に把握できるようになります。さらに、書類にはわかりやすいラベルを付けると便利です。例えば、「極秘」「秘」「社外秘」といったラベルを用いることで、書類の取り扱いミスや誤った廃棄を防げます。こうした工夫により、機密文書の保管と管理の効率を上げていきましょう。
機密文書の廃棄
機密文書の廃棄には、書類の重要度(レベル)に応じた適切な方法が求められます。極秘文書や秘文書など、情報漏えいが重大な影響を及ぼす可能性のある書類は特に注意して処分しなければなりません。廃棄の前に、まず書類が法的に保管義務のあるものではないかを確認し、さらに保管期間が満了していることを確かめます。
廃棄方法に関しては、社内で機密文書を処分する場合、シュレッダーを使用します。シュレッダーは小規模な書類廃棄には適しています。ただし、シュレッダーにはいくつかの限界があります。大量の機密文書を処分する際には時間がかかり、細断後の紙くずの管理も必要です。また、シュレッダーで細断された書類は、専門技術を使えば再構成される可能性があり、情報漏えいのリスクを完全に排除できるわけではありません。このような理由により、より厳密なセキュリティが必要な場合や大量の書類を処分する場合には、溶解処理の機密文書廃棄サービスが最もリスクが低いでしょう。
機密文書の廃棄を外部企業に任せる
機密文書の廃棄において、コスト、セキュリティ、環境保護などの観点から、専門の機密文書廃棄サービスを利用することは非常に効果的です。近年では、溶解処理が主流の廃棄方法として採用されており、これらの課題を一括して解決できる手段として注目されています。
廃棄方法や溶解処理の記事ならこちらの記事も参考にしてください。
書類保管サービスの「書庫番人」に機密文書の保管や廃棄を任せてみませんか?
機密文書の廃棄は、その重要度(レベル)に応じた適切な方法が求められます。書類保管サービスの「書庫番人」では、こうした機密文書を安心かつ効率的に保管、廃棄するサービスを提供しています。保管期間が満了した書類については、通知メールを通じて適切なタイミングで廃棄依頼が可能です。重要な機密文書も専用車両を使用した安全な輸送と、目に触れることなく行われる溶解処理で確実に廃棄されます。さらに、1箱600円というリーズナブルな価格設定や、初心者向けのサポート体制も整っており、企業規模を問わず利用しやすいサービスとなっています。
▼機密文書の保管に困っている方は、書類保管サービスもぜひご利用ください。