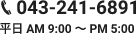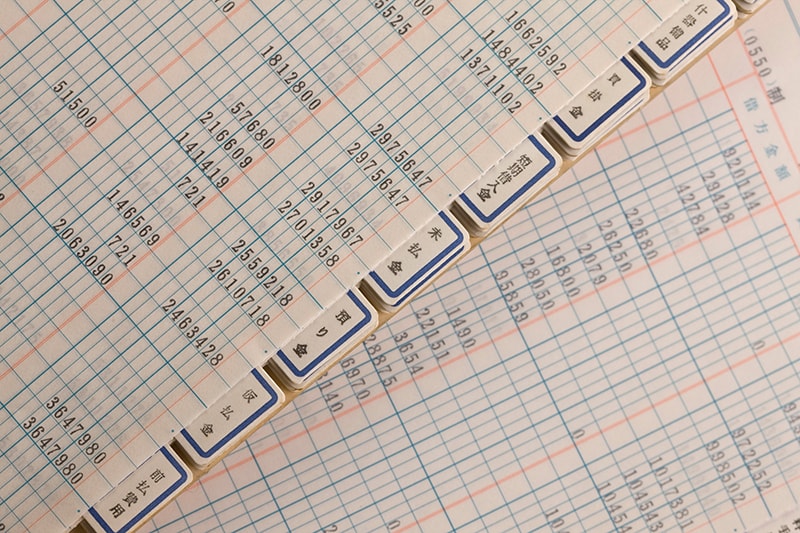企業での経理や書類管理で、仕訳帳の保存期間について迷っている方は多いのではないでしょうか。仕訳帳は日々の取引記録が詰まった大切な帳簿であり、適切な期間保存しなければ、税務調査や監査で思わぬトラブルに発展するかもしれません。本記事では、仕訳帳の保存期間やその注意点などを解説します。法令遵守しながら、保存期間を守り、安全に管理していきましょう。

書類保管サービス「書庫番人」でコスト削減
仕訳帳とは?
仕訳帳(しわけちょう)とは、企業が日々の事業活動で発生する全ての取り引きを記録する帳簿の一つです。お金の流れを日付順に記録し、会計処理の基盤を築く重要な役割を担っています。
帳簿の種類
| 主要簿 | 補助簿(補助元帳) | 補助簿(補助記入帳) |
|---|---|---|
| 仕訳帳 総勘定元帳 日記帳 | 商品有高帳 買掛金元帳 売掛金元帳 | 現金出納帳 預金出納帳 支払手形記入帳 受取手形記入帳 仕入帳 売上帳 経費帳 固定資産台帳 |
仕訳帳は、会計上で発生した取り引き(売り上げ、仕入れ、支払い、収入など)を記録するために欠かせないツールです。仕訳帳に取り引きを記載する際は「借方(かりかた)」と「貸方(かしかた)」の2つの項目に分けられ、各取引の内容や金額を記録します。仕訳帳は会計上の基本的な情報源となるため、正確に記録しましょう。仕訳帳をもとにして「総勘定元帳」や「試算表」など、会計処理の次のステップで必要となる高度な書類が作成されます。また、税務調査においても、仕訳帳は重要な確認資料となります。取り引きの履歴が詳細に記録されていれば、税務申告に対する信頼性が高まり、税務調査にスムーズに対応できるでしょう。
帳票や帳簿などの間違えやすい書類の違いを知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
仕訳帳の保存期間
仕訳帳は、企業の日々の取引を記録する大切な帳簿です。その保存期間については、法律によってしっかりと定められています。主に「法人税法」と「会社法」の2つの法律で保存期間が規定されています。これらの法律の違いを理解し、法令に従って正しく保存していきましょう。
法人税法の保存期間
法人税法では、企業が仕訳帳を含む会計帳簿を保存する期間について、所定の起算日から「7年間」保存しなければならないと定められています。具体的には、事業年度の確定申告書を提出する期限の翌日から起算して7年間、帳簿を適切に保存しなければなりません。しかし、事業年度で欠損金(赤字)が発生した場合、法人税法上の保存期間は「10年間」に延長されます。これらの保存期間は、仕訳帳だけでなく、取り引きの証拠となる証憑書類(領収書、請求書、契約書など)も含まれます。
法人は、帳簿を備え付けてその取り引きを記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。
参考:国税庁|No.5930 帳簿書類等の保存期間
会社法の保存期間
一方、会社法では、仕訳帳を含む会計帳簿の保存期間は「10年間」と定められています。会社法は、主に株式会社をはじめとする法人に適用されます。会社法の目的は、企業活動の透明性や健全性の確保です。
株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
参考:e-Gov法令検索|第四百三十二条2
保存期間を守る重要性
仕訳帳を適切に保存することの重要性は、主に以下の2点に集約されます。
1.税務調査への対応
税務署などの税務当局は、企業の税務申告が正しく行われているかを確認するために、過去の帳簿を調査します。仕訳帳は、日々の取り引きが全て記録された基本的な帳簿であり、税務調査の際には重要な証拠資料となります。もし、税務調査の際に必要な仕訳帳などの帳簿類が揃っていない場合、過去の申告に不備や誤りがあるとみなされるリスクが高まります。その結果、追加の税金や延滞税を支払うことになる可能性があるため、法定の保存期間は遵守しましょう。
2.監査への対応
上場企業や大規模な企業では、定期的に監査法人による会計監査が実施されます。監査では、仕訳帳や関連する会計帳簿が正確に保存され、取引内容が正当であるかが確認されます。適切に帳簿が保存されていない場合、監査報告書に不備や問題点として指摘される可能性があります。このような指摘があると、企業の信用低下や投資家の不信感につながってしまうかもしれません。そのため、監査にしっかり対応できる体制を整えておきましょう。
保存期間に関する注意点
仕訳帳を保存する際には、保存期間が異なる法律や書類が関係してくるため、注意が必要です。
保存期間が異なる法律
仕訳帳の保存期間は、法人税法と会社法で異なるため、どちらの法律に基づいて保存するべきかを正しく判断しなければなりません。法人税法では「7年間」の保存が義務付けられており、一方で会社法では「10年間」の保存が求められています。同じ仕訳帳であっても、適用される法律によって保存期間が異なるため、企業はそれぞれの法的要件に従う必要があります。
保存期間が長いほうに合わせる
仕訳帳の保存期間に迷った場合は、最も長い期間で保存するのが一般的です。具体的には、法人税法で「7年間」会社法で「10年間」と定められているため「10年間」保存することが推奨されます。さらに、法人税法では欠損金が発生した事業年度に関しては、保存期間が10年間となります。そのため、日常的に10年間保存するようにすれば、どちらの法律にも対応でき、法令違反のリスクを回避できるでしょう。保存期間を長めに設定することで、万が一、税務調査や会計監査が行われた場合でも、余裕を持った対応ができるため、重要な書類が不足する心配がなくなるでしょう。適切な保存は、企業の信頼維持やスムーズな経営管理にもつながります。
他の帳簿や個人事業主の場合の保存期間と間違わない
仕訳帳以外にも、さまざまな帳簿や書類が存在しており、書類によっては法律で決まっている保存期間が違うものがあります。例えば、個人事業主の場合、帳簿や書類の種類によっては「5年間」の保存で問題ないものもあります。具体的には、請求書の控え、見積書、契約書、納品書の控え、注文書などの取り引きの過程でやり取りした書類は、個人事業主の場合「5年間」の保存が義務付けられています。一方、法人の場合は会社法に基づき、仕訳帳を含む会計帳簿や関連書類を「10年間」保存しなければなりません。法人の場合は、他の帳簿や個人事業主の保存期間と混同しないよう、常に「10年間」の保存を意識していきましょう。
保存期間が過ぎた仕訳帳の廃棄
仕訳帳は、法人税法や会社法に基づいて定められた期間保存する義務がありますが、その期間を過ぎれば廃棄することができます。ただし、廃棄方法には注意が必要です。誤った方法で廃棄すると、取引情報や機密情報が漏洩するリスクが高まるため、安全かつ適切な方法で廃棄し、企業の情報を守っていきましょう。
社内でのシュレッダー処理
シュレッダー処理は、最も一般的で手軽な書類廃棄方法です。保存期間が過ぎた仕訳帳を自社内でシュレッダーにかけることで、情報漏洩のリスクを防げるでしょう。しかし、シュレッダーを使用する際には注意点があります。大量の書類を処理する際、時間と労力がかかります。さらに、復元されるリスクも考慮しなければなりません。
機密文書廃棄サービスの利用
仕訳帳を含んだ大量の書類を廃棄する場合、自社内で処理するのは難しいかもしれません。そのような場合は、機密文書廃棄サービスを利用するのも一つの方法です。書類の廃棄サービスは多数あるため、信頼性の高さを重視して選ぶことが重要となってきます。
機密文書廃棄サービスの選定ポイント
仕訳帳の機密文書廃棄サービスを選ぶ際には、セキュリティ対策と信頼性を最優先に考えましょう。まず、廃棄後に証拠としての記録が必要になることもあるため、廃棄証明書を発行してくれるか確認します。次に、大量の仕訳帳を処分する際は、業務負担を軽減できるかも確認しましょう。例えば、書類の回収から廃棄までを一括で任せられるかは重要になってきます。さらに、外部企業と契約する際は、セキュリティ対策が十分かを確認することが不可欠です。廃棄の過程で情報漏洩が発生しないよう、厳重な管理体制が整った機密文書廃棄サービスを選びましょう。中でも、機密性の高い仕訳帳には、溶解処理が最適です。溶解処理は、書類を細かく裁断する必要がなく、そのまま溶解するため、セキュリティリスクを最小限に抑え、安全に廃棄できます。
書類保管サービスの「書庫番人」に仕訳帳の管理を任せてみませんか?
仕訳帳の管理は法的な保存期間を守る必要があり、企業にとって重要ですが、保存や廃棄作業は手間がかかります。書類保管サービスの「書庫番人」を活用することで、仕訳帳や会計帳簿を安全に保存し、必要なときに迅速にアクセスできます。「書庫番人」は高度なセキュリティと厳格なアクセス管理で、保存期間が終了した帳簿の安全な廃棄も提供します。溶解処理により、情報漏洩の心配なく、簡単に処理が完了します。さらに、リーズナブルな価格で、書類管理の手間を大幅に削減し、業務効率を向上させます。仕訳帳の管理を専門家に任せて、安心して業務に集中してみませんか? お問い合わせよりお気軽にご相談ください。