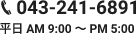納品書は売り手が発行し、納品した商品やサービスの内容を伝えるための書類です。一方、受領書は買い手が発行し、納品物を受け取ったことを証明するために使われます。本記事では、それぞれの役割や記載すべき項目、保管義務、適切な保存方法について詳しく解説します。

書類保管サービス「書庫番人」でコスト削減
納品書と受領書の違い①目的と役割
ビジネスの現場では、納品書と受領書は取り引きの証拠として重要な役割を担います。これらの書類を正しく理解し、適切に運用することが、円滑な取引関係を築くために欠かせません。そこで、それぞれの目的と役割について詳しく解説します。
納品書とは?その目的と役割
納品書は、売り手が商品やサービスを納品する際に、買い手へ発行する書類です。
主な目的は、納品した商品やサービスの内容や数量を明確に伝え、買い手が注文内容と照らし合わせて確認できるようにすることです。この書類を活用することで、納品ミスや数量の誤りを防ぎ、取り引きの透明性を高める役割を果たします。
受領書とは?その目的と役割
受領書は、買い手が商品やサービスを受け取ったことを証明するために、売り手へ発行する書類です。
主な目的は、納品物を確実に受領したことを記録し、のちのトラブルを防ぐことです。特に、納品物の受け取りに関する誤解や紛争を未然に防ぐための証拠として機能します。
納品書と受領書の違い
納品書と受領書の主な違いは、発行者と目的にあります。納品書は売り手が発行し、納品内容を伝えることが目的です。一方、受領書は買い手が発行し、納品物を受け取ったことを証明するために使用されます。さらに、納品書は納品時に発行されるのに対し、受領書は納品物を受け取ったあとに発行されます。このように、両者は取り引きの異なる段階で、それぞれの立場から取り引きの事実を記録し、証明する役割があるのです。
| 項目 | 納品書 | 受領書 |
|---|---|---|
| 発行者 | 売り手 | 買い手 |
| 目的 | 納品内容を伝える | 納品物を受け取ったことを伝える |
| 発行タイミング | 納品時 | 受け取ったあと |
納品書と受領書の違い②記載項目
取り引きを円滑に進めるためには、納品書や受領書を正しく作成し、必要な情報を記載することが重要です。これらの書類は、取り引きの証拠となるだけでなく、のちのトラブルを防ぐ役割も果たします。それぞれの書類に記載すべき主な項目について解説します。
納品書に記載すべき情報
納品書は、商品やサービスの納品内容を明確に記録するための書類です。適切に作成することで、取り引きの透明性を高め、誤解やトラブルを防ぐことができます。一般的には、次の情報を記載することが望ましいです。
- 発行者の情報(会社名、住所、連絡先など)
- 取引先の情報(会社名、担当者名など)
- 発行日
- 納品日
- 取引内容(商品やサービスの名称、数量、単価、金額)
- 取引金額(税込)
- 納品書番号(管理しやすくするため)
- 備考欄(特記事項や納品場所の指定など)
特に、仕入税額控除を適用するためには、適格請求書の要件を満たす書類(インボイス)が必要です。納品書そのものにはインボイスとしての発行義務はありませんが、請求書や領収書と併せて適切に記載することが求められます。
受領書に記載すべき情報
受領書は、納品された商品やサービスを確かに受け取ったことを証明する書類です。納品書と共通する項目が多いものの、受領の証拠としての役割があるため、正確な記載が必要です。
- 発行者の情報(会社名、住所、連絡先など)
- 受領者の情報(会社名、担当者名など)
- 発行日
- 受領日
- 取引内容(商品やサービスの名称、数量、単価、金額)
- 受領書番号(納品書との照合をしやすくするため)
- 受領者の署名または押印
- 備考欄(特記事項や受領時の注意点など)
受領書には法的な発行義務はありませんが、取り引きの証拠として残しておくことで、のちのトラブルを防ぐことができます。また、取引先によっては印鑑を求められる場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。
法的に必要な項目はある?
納品書と受領書は、請求書や領収書とは異なり、法律で発行が義務付けられているものではありません。そのため、記載すべき項目に関する法的な規定もありません。しかし、税務調査などで取り引きの証拠として提出を求められる場合があるため、取引内容を正確に記載することが大切です。また、インボイス制度の導入により、適格請求書の発行が求められるケースでは、納品書や受領書と請求書を組み合わせることで、要件を満たすことが可能です。こうした背景を踏まえ、各企業において適切な運用方法を検討する必要があります。
納品書と受領書の違い③保管義務と保存期間
企業や個人事業主が行う取り引きでは、納品書や受領書が証憑書類として重要な役割を果たします。これらの書類は、税務処理や会計管理の際に必要となるため、適切に保管しなければなりません。また、法人と個人事業主では保管義務や保存期間が異なるため、正しく理解し、管理することが大切です。
納品書の保管義務と保存期間
納品書は、法人税法および所得税法に基づき、取り引きの証拠となる重要な書類です。税務調査の際には、取り引きの正当性を証明する資料として求められることがあるため、法律で定められた期間の保管が必要です。法人と個人事業主で異なる保存期間について、以下の内容を参考に適切に管理しましょう。
法人の場合
7年間の保管義務がある
欠損金(赤字)の繰越控除を適用する場合、最大10年間の保存が必要(平成30年4月1日以降の事業年度が対象)
納品書は、請求書や領収書と一緒に保管することで、税務処理の手間を削減できます。特に、赤字の繰越控除を適用する場合は、事業年度ごとに適切に管理することが望ましいです。
受領書の保管義務と保存期間
受領書は、取り引きの証憑書類の一つですが、納品書とは異なり、発行自体が法律で義務付けられているわけではありません。しかし、発行した場合は適切に管理する必要があります。受領書は納品書と照合することで取引内容の整合性を確認する際に役立つため、一定期間の保管が推奨されます。
法人の場合
7年間の保管義務がある
欠損金の繰越控除を適用する場合、最大10年間の保存が必要
保管期間の起算日は確定申告期限日の翌日
受領書は納品書とともに保管することで、取引履歴を明確にできます。適切に分類し、管理することで、税務処理の際の手間を減らすことができます。
納品書・受領書の適切な保管方法
納品書や受領書は、税務処理や取り引きの証拠として重要な書類であり、適切な保管が求められます。しかし、日々増え続けるため、管理の手間や保管スペースの確保が課題となることが少なくありません。
紙媒体での保管方法
納品書や受領書は、電子化が進んでいるとはいえ、今なお紙で発行されることが多い書類のため、適切な管理が必要です。以下の方法を取り入れることで、効率的に整理できます。
・事業年度ごとの分類
事業年度ごとに分類し、ファイルやクリアポケットにまとめて保管します。年度ごとに管理することで、税務調査や会計監査の際にもスムーズに対応可能です。適切に分類しておくことで、必要な書類をすぐに取り出せるようになり、業務の負担を軽減できます。
・取引先ごとの整理
取引件数が多い場合は、取引先ごとにファイリングする方法が有効です。取引先ごとに書類をまとめておくと、過去の取引内容を確認しやすくなり、取引履歴を簡単に把握できます。
・保管スペースの確保
納品書や受領書は、年月が経つにつれて増えていくため、適切な保管スペースを確保することが重要です。専用のキャビネットや書庫を活用し、整理整頓を徹底することで、必要な書類をすぐに取り出せるようになります。また、書類が増えすぎると、オフィスのスペースを圧迫するだけでなく、管理が煩雑になりやすいため、定期的に整理を行うことも大切です。
・保管期間が過ぎた書類の適切な処理
納品書や受領書には法定の保管期間があります。期間を超えた書類を処分する場合、適切に廃棄しましょう。機密情報を含む書類を処分する際は、シュレッダーを使用するか、専門の廃棄業者に依頼するのが望ましいです。特に、個人情報や機密情報を含む書類は、適切に処理しなければ情報漏洩につながる可能性があるため、十分な注意が必要です。
書類保管サービスの活用
納品書や受領書を紙のまま保管し続けると、書類の増加により管理の負担が大きくなります。特に長期保存が必要な企業や、取引量の多い企業にとっては、整理が大きな課題となるでしょう。そのような場合には書類保管サービスの活用が有効です。このサービスを利用すると、専門業者が書類を安全に保管・管理するため、オフィスのスペースを節約できます。さらに、書類の検索や取り出しがスムーズになり、保管期限の管理も容易になります。期限を過ぎた書類は自動で廃棄されるため、不要な書類の処理に手間をかける必要がありません。また、セキュリティ対策が施されているため、紛失や盗難のリスクを最小限に抑えられます。特に重要書類や契約書の保管に適しており、情報管理の強化にもつながります。
納品書・受領書の管理は書類管理サービス「書庫番人」にお任せください
「書庫番人」は、初めての方でも安心して利用できるコンシェルジュ型の書類保管サービスです。専属のコンシェルジュが、状況に応じて最適な保管方法を提案し、トータルコストの削減を実現します。また、機密文書に強く、経理書類・総務書類、契約書、個人情報書類、カルテなど、さまざまな書類の保管に対応しています。さらに、書庫番人では、導入前に無料コンサルティングを行い、書類保管状況から最もコストのかからない運用方法を提案します。これにより、保管から廃棄までのトータルコストを抑えることが期待できます。納品書・受領書の適切な管理をサポートします。納品書や受領書の保管に悩んでいる方は、ぜひ「書庫番人」の書類保管サービスをご検討ください。