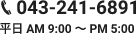看護記録の作成や保存には法的ルールや倫理的配慮が求められ、適切に管理することが医療現場の信頼性と安全性を支える基盤となります。本記事では、看護記録の基本から法的な保存義務、適切な保存方法、そしてその重要性について詳しく解説します。

書類保管サービス「書庫番人」でコスト削減
看護記録は法的にはどんな書類?
看護記録は、その性質上、看護記録には患者の個人情報が含まれるため、守秘義務が課せられています。情報を共有する際は細心の注意を払い、特に外部への情報漏洩を防ぐ対策が重要です。
看護記録は、健康保険法および医療法によって定められた公的な記録です。医療法第21条では診療に関するさまざまな記録が規定されており、医療法第22条の2では特定機能病院が備える診療記録について記されています。これらの規定には看護記録も含まれています。
看護記録の保存期間と法的ルール
看護記録の保存には法的義務があり、保存期間や基準は記録の種類や目的によって異なります。法令を正しく理解することが、業務を効率的に進めるための重要なポイントです。
| 記録名 | 保存期間 | 法的根拠 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 看護記録 | 3年間 | 保険医療機関および保険医療養担当規則 | 保険医療機関が作成した診療録以外の看護記録 |
| 看護記録 | 2年間 | 医療法施行規則 | 医療機関が作成した看護記録 |
| 訪問看護などの提供記録 | 2年間 | 指定居宅サービスなどの事業の人員、設備および運営に関する基準指定訪問看護の事業の人員および運営に関する基準 | 主治医による指示書、訪問看護計画書、訪問看護報告書など |
保存期間を超えた看護記録の保存の重要性
法定期間を超えても看護記録を保存することが推奨される場合が多く見受けられます。特に、医療事故やトラブルが発生した際には、看護記録が重要な証拠として活用され、医療機関の信頼を守るうえで大きな役割を果たします。
例えば、看護記録は、医療ミスが疑われた場合に無実を証明するための書類として利用できます。損害賠償請求の消滅時効は、「被害者が損害賠償請求できると知った時から5年間、医療行為が行われた時から20年間」とされています。このため、記録を20年間保存しておくと、安心といえるでしょう。
看護記録の廃棄が推奨されない理由
看護記録は、医療現場における信頼性と透明性を支える非常に重要な存在です。そのため、損害賠償請求の消滅時効である20年間が経過する前に廃棄することは、多くのリスクを伴うため、推奨できません。
特に懸念されるのは、記録の改ざんを疑われる可能性が高まる点です。紙媒体であれ電子媒体であれ、看護記録が欠落している場合、意図的に改ざんされたと見なされる危険性が生じます。過去の診療内容や患者の経過を正確に把握できなければ、医療機関が正当性を主張することが困難になる場合もあります。そのため、記録の完全性を保つことは、患者だけでなく医療従事者や医療機関を守ることにもつながります。
どうしても廃棄が避けられない状況では、廃棄する前の情報をきちんと保存し、その後の状態も記録する対応が求められます。この手続きを怠ると、記録の正確性が損なわれるだけでなく、トラブルが発生した際に不利な立場に立たされるリスクが高まります。
看護記録の廃棄は慎重に行う必要があり、可能であれば20年間は廃棄を避けることが信頼性と透明性を守る最善の方法といえるでしょう。
看護記録の保存方法と選択肢
看護記録や診療録などを保存する場所については、記録を作成した病院や診療所で保管するのが一般的です。
ただし、厚生労働省の通知に基づき、条件を満たす場合は院外での保管も認められています。さらに、診療録などの記録は電子媒体で保存することも可能です。
記録の保存方法には複数の選択肢があり、それぞれのメリットや注意すべき点を理解することが大切です。
方法1:院内・施設内での直接保存
院内や施設内で直接保管する方法は、看護記録を保存する上で最も伝統的な手法です。この方法では、紙媒体の記録を専用の保管室やキャビネットに収め、職員が必要に応じてアクセスできるようにしています。
この手法の主な利点は、記録が物理的に近くにあるため、急な確認が必要な場合でもすぐに利用できる点です。また、保管場所を医療機関が直接管理することで、記録の安全性が向上します。さらに、紙媒体は電気やシステム障害の影響を受けないという特長も挙げられます。
一方で、直接保管にはいくつかの課題もあります。特に大きな問題は、スペースの確保です。看護記録は患者ごとに詳細に記録されるため、長期間にわたる記録が蓄積すると非常に多くの保管場所を必要とします。このため、限られたスペースを効率的に活用するには、記録を定期的に整理し、アーカイブ化する作業が不可欠です。
方法2:電子化を活用した院内保存
近年、多くの医療機関で採用が進められているのが、電子化による院内保存です。電子カルテや電子看護記録システムを利用することで、看護記録をデジタル形式で保存する方法が広がっています。この方法により、物理的なスペースに関する課題が大幅に軽減される点が大きな特徴です。
電子化の主なメリットとしては、迅速な情報検索や共有が挙げられます。例えば、診療中に必要な情報をシステム上で即座に検索でき、複数の医療従事者間でリアルタイムに情報を共有することが可能です。また、記録のバックアップを取ることで、災害時や予期せぬトラブルにも対応できる体制を整えることができます。
一方で、電子化には導入や運用にかかるコストが発生する点に注意が必要です。システムの初期投資だけでなく、継続的なメンテナンスや職員に対する研修も求められます。さらに、データセキュリティを強化することも重要な課題であり、不正アクセスや情報漏洩を防ぐための適切な管理体制が必要です。
看護記録を電子化する際には、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(e-文書法)に基づき、以下の基準を満たすことが求められます。
1.真正性の確保
記録が正当な権限の下で作成され、改ざんや不正操作が防止されていることが必要です。そのためには、アクセス制御やユーザー認証の実施、操作履歴の記録が求められます。
2.見読性の確保
保存された記録をいつでも正確に閲覧できる状態を維持する必要があります。長期保存に適したフォーマットを選択し、システムの保守やバックアップを行うことが推奨されます。
3.保存性の確保
保存期間中、記録の安全性を保ち続けることが求められます。適切なデータ保護策や媒体管理を実施し、記録が劣化や消失しないように管理する必要があります。
これらの基準を満たすことで、電子化された看護記録は法的な信頼性を確保し、医療の質を向上させることが可能です。特に、データの保全と長期的な利用を可能にする環境の整備が重要です。一般的な電子システムであれば、これらの基準をほぼ満たすことができます。ただし、クラウドシステムを使用していない場合には、バックアップなどの管理が別途必要となります。
参考:e-文書法|民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
方法3:外部サービスを活用した書類保存
看護記録を含む紙の医療書類を外部の書類保管サービスで管理する方法は、スペースや管理コストに課題を抱える医療機関にとって有効な選択肢です。このサービスでは、記録を安全に保存し、必要に応じて迅速に配送する体制が整っています。
この方法を活用すると、保存義務のある看護記録だけでなく、その他の重要な医療書類も一括して効率的に管理できます。ただし、外部保存を実施する際には、以下の基準を満たす必要があります。
紙媒体・電子媒体共通の基準
- 個人情報保護法などを遵守し、患者のプライバシーを確実に保護すること
- 保存義務を有する医療機関が責任を持って外部保存を行うこと
電子媒体による保存の場合
- 記録の真正性、見読性、保存性を確保すること
- 情報処理機器が適切に管理された安全な場所で運用されること
紙媒体のまま外部保存を行う場合
- 必要なときに速やかに利用できる体制を整えること
外部の書類保管サービスは、管理の負担を軽減しつつ、適切な基準を守ることで安心して活用できる選択肢といえます。
参考:厚生労働省保険局長通知|診療録等の保存を行う場所について〔医療法〕
看護記録の保存は「書庫番人」の書類保管サービスに任せてみませんか?
「書庫番人」は、看護記録の保存に特化したプロフェッショナルサービスを提供し、医療現場のニーズに応えるトータルサポート型の書類保管ソリューションです。はじめて利用する方でも安心してご依頼いただけるよう、専属のコンシェルジュが保存期間や法的要件に基づいた最適なプランを提案します。院内スペースの有効活用、セキュリティ強化、管理業務の効率化を実現するだけでなく、不要となった記録の適切な処理やデジタル化にも対応。看護記録管理に伴う負担を大幅に軽減し、現場に安心とゆとりをもたらします。
看護記録の保存に関するお悩みを解決したい方は「書庫番人」の書類保管サービスをぜひご検討ください。お問い合わせフォームからお悩みをご相談いただければ、適切な保管の提案をいたします。
▼書庫番人の業種別活用シーンもぜひご覧ください。