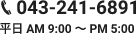e-文書法による法定保管文書の電子化は多くの企業が取り組むべき課題ですが、適切な運用ルールを理解していなければコンプライアンス違反や情報セキュリティのリスクを招く恐れがあります。本記事では、e-文書法の基本概念、電子保存の具体的な要件、導入時のポイントなど、企業の書類管理担当者が押さえておくべき知識を紹介します。

書類保管サービス「書庫番人」でコスト削減
e-文書法とは
e-文書法は、法律や規則で保管を義務付けている帳簿、領収書などの書類を紙だけではなく電子化したファイル(電磁的記録)で保管することを認める法律です。「電子文書法」とも呼ばれています。e-文書法は通称であり、正式には2005年4月に施行された2つの法律を指します。
- 「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(通則法)
- 「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(整備法)
通則法は電子保存の一般的なルールを定めており、整備法は通則法ではカバーしきれない部分を一部改正して、ルールを整備しています。通則法が対象となる法律は、商法、会社法、各種税法(地方税法、所得税法、法人税法など)、銀行法、保険業法、労働基準法、学校教育法など約250本にもおよびます。
e-文書法の制定背景
e-文書法は2005年4月に施行されました。その背景には1990年代後半からの電帳法による税務関連帳簿の電子化、2000年頃におきたIT化推進があります。しかし当時は一部書類の紙での保管が義務付けられ、企業活動の効率化を妨げていました。日本経団連をはじめとする民間企業からの要望と情報通信技術の進展を受け、2004年に政府は電磁的記録による保管を認める方針を策定しています。これにより約250の法律を個別改正せずに電子保存ができるようになり、さらに約70の個別法の改正も行われ、電子化の範囲が大幅に拡大されました。
e-文書法の対象書類
e-文書法は、多くの法定保管書類を対象としており、関連する法律や管轄する省庁も複数におよびます。通則法により、民間企業が法令で紙での保管を義務付けられている書類は、原則として全て電子保存が可能です。
e-文書法の対象となる主な書類
- 国税関係帳簿:総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳など
- 取引関係書類:契約書、見積書、納品書、請求書、領収書など
- 決算関係書類:貸借対照表、損益計算書、棚卸表など
- 会社関係書類:株主総会議事録、取締役会議事録、定款など
- その他:預金通帳など
これらはあくまで代表的な例であり、法令で保管が義務付けられている書類の大部分が対象となっています。
e-文書法の対象外となる書類
- e-文書法施行前にすでに電子保存が認められていた書類
- e-文書法施行後に制定された法律の書類
- 緊急時に即座に閲覧する必要がある書類(機械や乗り物の手引書:船舶に備える安全手引書など)
- 極めて現物性が高い書類(免許証・許可証など)
- 条約により保管が義務付けられている書類
書類によっては電子化が認められていない場合もあるため、電子データ化して保管する際には事前に確認するとよいでしょう。
e-文書法で求められる4つの電子保存要件
e-文書法で書類を電子保存する場合、各府省の主務省令で定められた要件を満たさなければいけません。これは紙の書類と電子データの性質が根本的に異なるためです。
- 見読性:保管された情報をすぐに閲覧できる状態を維持すること
- 完全性:データの改ざんや消失を防ぐための対策を講じること
- 機密性:不正アクセスや情報漏洩を防止すること
- 検索性:必要な情報を迅速に検索・取得できるようにすること
見読性
電子データそのものは人間が直接目で見て内容を理解することはできないため、必要なときにすぐに内容を確認できる環境を整えなければいけません。
- コンピュータ画面上で内容を正確に表示できること
- 必要に応じて書面に出力して確認できる体制を整えること
- 保管されたデータが破損せず、常に読み取り可能な状態を維持すること
完全性
電子データは物理的な実体がないため、改ざんや破損のリスクは紙の書類より高くなります。そのため、それを避ける仕組みが必要になります。
- データの破損、改変、不正な削除などを防止するシステムの構築
- 万が一の改ざんを検知できる仕組みの導入
- システム操作の履歴(アクセスログ、変更履歴など)を記録すること
- 書き換え不可能な記録媒体の使用、定期的なバックアップの実施
- 電子署名、タイムスタンプを活用したデータの作成者・作成時刻の証明
機密性
電子データはサイバー攻撃などの脅威にさらされる可能性があります。セキュリティ対策を行うことが必要です。
- 適切なアクセス権限の設定と管理
- 強固なパスワードポリシーの策定と実施
- データの暗号化などによる保護措置
- セキュリティ教育と厳格な運用ルールの確立
検索性
紙の書類と同様に、電子保存されたデータも体系的に整理して、大量のデータの中から必要な情報に素早くアクセスできる環境を整えましょう。
- 論理的なフォルダ構造や命名規則の確立
- メタデータ(作成日、書類の種類、関連情報など)の付与
- キーワード検索などの機能の実装
- インデックス作成による検索速度の向上
電子保存要件を導入する際の注意点
電子保存の要件は、全ての書類に均一に適用されるわけではありません。中でも、完全性、機密性、検索性の3つの要件は、通常の紙での保管と比べて負担が大きいため、全ての電子書類ではなく、医療機関のカルテや税務関連書類などの特に重要度の高い書類にのみ適用されています。
見読性:基本的に全ての電子書類に求められる基本要件
完全性・検索性:一部の重要書類(国税関係書類など)にのみ厳格に適用される要件
機密性:現時点では明確な法的根拠による保存要件とはなっていないが、情報セキュリティの観点を考慮すると重要
電子署名とタイムスタンプ:電子書類の信頼性を高める技術
電子署名とタイムスタンプは、4つの保存要件のうち特に「完全性」と「機密性」を確保するための重要な技術です。これらの要件は全ての電子書類に法的義務があるわけではないですが、情報セキュリティ強化や証拠能力向上のため、多くの企業で活用されています。
電子署名の役割
電子署名は、電子書類の作成者の本人性と内容の真正性を保証します。2001年4月施行の電子署名法により、適切に管理された電子署名付きの書類には法的効力が認められました。電子署名法3条では、一定要件を満たす電子署名が付された電磁的記録には「本人作成」の推定効が働くと規定されています。これにより、正規の電子署名付きの書類は、本人が作成し改ざんされていないことを主張できる法的根拠となります。
タイムスタンプによる時刻証明
タイムスタンプは、電子データが「特定日時に存在していたこと」および「そのあと改ざんされていないこと」を証明する技術で、信頼できる時刻認証局が発行します。電子書類にタイムスタンプを付与することで、作成・受領時期を客観的に証明でき、紛争や監査時の有力な証拠となります。中でも、契約書や重要業務記録など、時期の立証が重要な書類に有効です。
電子帳簿保存法とe-文書法の比較
電子帳簿保存法(電帳法)とe-文書法は、どちらも書類の電子化・電子保存に関する法律ですが、対象範囲や要件に違いがあります。両法律の大きな違いは、電帳法が国税関係の書類に特化した専門的な法律であるのに対し、e-文書法はより広範な法定書類の電子化を可能にする包括的な法律という点です。企業が書類電子化を検討する際は、対象書類がどちらの法律に該当するかを正確に把握し、それぞれの要件に沿った対応を行うとよいでしょう。
対象とする書類の範囲の違い
電子帳簿保存法(電帳法)
- 国税関係帳簿書類と電子取引を対象とする法律
- 総勘定元帳、仕訳帳などの帳簿類、貸借対照表
- 損益計算書などの決算関係書類
- 納品書、請求書などの取引関係書類
- 電子契約などの電子取引で授受した書類
- 管轄は財務省・国税庁のみ
e-文書法
- 約250もの法律にまたがる幅広い法定書類が対象
- 会社法、商法、医療関係、建築関係、保険関係など多岐にわたる
- 管轄省庁も厚生労働省、経済産業省、内閣府、法務省、警察庁など多数
保管要件の違い
電子帳簿保存法
- 「真実性」と「可視性」の2要件を中心に細かく規定
- 真実性:改ざん防止や証明機能に関する要件
- 可視性:閲覧や検索機能に関する要件
- 電帳法規則の詳細な技術的・運用的要件が定められている
e-文書法
- 「見読性」「完全性」「機密性」「検索性」の4要件が基本
- ただし実際には見読性のみが求められる書類も多い
- 書類の種類によって主務省令で具体的な要件が定められる
書類の電子化のメリットと導入時の注意点
e-文書法に基づく書類の電子化は、企業に多くのメリットをもたらす一方で、導入にあたっては注意すべき点もあります。
書類の電子化の主なメリット
コスト削減面では保管スペースや管理にかかる費用の軽減が期待できます。業務効率面では書類の検索・共有の迅速化やリモートワーク対応が可能になります。さらに災害時のデータ保全や環境負荷低減などの付加価値も得られるでしょう。
導入時の注意点
システム導入、運用設計にかかる初期投資、業務プロセスの見直し、社員教育の必要性、電子データ特有のセキュリティ対策などを考慮しなければいけません。e-文書法対応で業務効率化を図るメリットは大きいですが、適切なシステム導入、プロセス整備にはコストや手間がかかることも念頭に置いておきましょう。
書類保管サービスの「書庫番人」に書類の管理を任せてみませんか?
e-文書法の対応や書類電子化を検討している企業の皆様、膨大な紙の書類管理にお悩みではありませんか。一度に電子化が難しい場合には「書庫番人」が電子化する書類と紙保管する書類のバランスを考慮し、企業に合わせた管理方法を提案します。もちろん、全て紙のままでの保管も任せてください。温度・湿度管理された専用施設で法定保管期間が必要な書類も安心して保管します。専門コンシェルジュによる対応と、機密文書廃棄サービスも格安でご利用いただけます。書類管理の悩みから解放されるよう、まずは「書庫番人」にご相談ください。