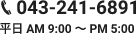貿易取引には、さまざまな書類が必要になります。この記事では、貿易関係の書類とその保管期間をわかりやすくまとめました。事後調査などに備え、しっかりと保管期間を守って書類を保管できるようにしましょう。

書類保管サービス「書庫番人」でコスト削減
保管が必要な貿易関係の書類とは?
貿易を行うときには、さまざまな書類が発生します。税関に提出したものを除き、貿易取引上発生したすべての書類を保管しておくことを考えましょう。貿易関係の書類は法律によって保管が義務づけられているため、すべて保管できていなければ法律違反となってしまいます。
また、貿易取引をした企業には事後調査というものが実施されます。事後調査とは、輸出入をしたときに輸出入手続きを正しく行っているかを確認する調査のことです。事後調査は3~5年程度の間隔で行われることが多いようです。事後調査では、貿易関係の書類をしっかり保管しているかどうかだけでなく、お金の流れや、取引相手とのやりとりもチェックされます。「この書類は必要なのかな?」と思った場合には、保管しておいた方がよいといえるでしょう。なお、国際宅配便などでは必要書類が届かないということもあります。もし必要書類が届かなかった場合には、取引相手から必ず取り寄せるようにしましょう。保管すべき書類を保管しておかなかった場合には罰則規定もあります。
貿易関係の書類などの保管期間まとめ
貿易関係の書類などは、関税法や規則により保管が義務づけられています。
ざっくり以下のように覚えておくとよいでしょう。
- 帳簿(輸入7年間保管、輸出5年間保管)
- 関係書類:輸出入許可書およびインボイスなど(5年間保管)
- 電子取引情報:電子メールやチャットなどを含む(5年間保管)
なお、貿易取引のみを行っている企業や個人事業主であれば、あえて帳簿を作成しなくても、「インボイスに輸出入許可の番号や日付を追記したもの」を帳簿のかわりとして保管することも可能です。
▼貿易関係以外の書類の保管期間についてはこちらをご覧ください
貿易関係の書類などの保管期間の詳細は、以下の表をご確認ください。
| 書類の種類 | 輸入 | 輸出 |
| 貿易に関する帳簿(品名、数量、価格、仕出人の氏名、輸入許可年月日、許可書の番号が記載されたもの) ※必要事項が網羅されている既存帳簿、仕入書等に必要項目を追記したものでも可 ※貿易に関する帳簿以外の帳簿は会社法・税法によって保管期間が定められています 1.会計帳簿および事業に関する重要書類:10年間 2.取引に関する帳簿:7年間 | 7年間 (輸入の許可の日の翌日から起算) | 5年間 (輸出の許可の日の翌日から起算) |
| 輸出許可通知書、輸入許可通知書、納税証明書、インボイス、仕入書、包装明細書(パッキングリスト)、価格表、B/L、アライバルノーティス(A/N)など | 5年間 (輸入の許可の日の翌日から起算) | 5年間 (輸出の許可の日の翌日から起算) |
| 原産地証明書 | 5年間 (輸入の許可の日の翌日から起算) | 3年~5年間 それぞれの国の協定によって異なる (発給日の翌日、もしくは申告書作成日から起算) |
| 輸入に関する製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、税関長に対して輸入の許可に関する申告の内容を明らかにする書類(総勘定元帳、補助台帳、補助簿、振替伝票、決済書類等の経理関係書類や発注関係書類、契約書、保険・運賃等の明細書、往復文書等の貿易関係書類、通関関係書類) | 5年間 (輸入の許可の日の翌日から起算) | – |
| 輸出に関する製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、税関長に対して輸出の許可に関する申告の内容を明らかにする書類(発注関係書類、往復文書等の貿易関係書類、通関関係書類) | – | 5年間 (輸出の許可の日の翌日から起算) |
| 電子取引の取引情報 (電子取引を行った場合における当該電子取引の取引情報) | 5年間 (輸入の許可の日の翌日から起算) | 5年間 (輸出の許可の日の翌日から起算) |
【注意】電子取引の取引情報を保管しよう
事後調査では、帳簿や輸出許可通知書などの書類の他に、貿易取引を行ったメールなども「電子取引の取引情報」としてチェックされます。保管義務もあるため、5年間保管できる環境を整えなければなりません。
スマートフォンのアプリなどでメールのやりとりをしている場合、古いメールを自動削除する設定になっていることもあります。アプリのアップデートなどで古いメールが消えてしまう可能性もありますので、必ず別途ハードディスクなどに保管する必要があります。
貿易関係の書類の保管方法
貿易関係の書類はすべて保管しなければならないため、管理の手間や保管スペースの確保が必要になります。基本的に「紙の書類は紙のまま保管・電子でやりとりした書類などは電子保管」とすると、管理が楽かもしれません。
なお、紙の書類をスキャナなどで読み取って電子データとして保管することも可能です。e-文書法や電子帳簿保存法の要項を守って、正しく保管しましょう。
▼税関の資料に詳しく記載されています
貿易関係の書類の取り扱いに困ったら
事後調査以外で使用することのない貿易関係の書類の保管に困っているなら、書類保管サービスの利用がオススメです。普段は書類保管サービスの倉庫に書類を預けておき、事後調査で必要になった際にだけ取り寄せればよいため、管理が簡単です。
貿易関係の書類の保管方法がわからなかったり、電子保管に取り組もうか悩んでいたりする場合には、コンシェルジュ型書類保管サービス「書庫番人」に是非一度ご相談ください。書類の保管状況などに応じて適切な保管方法のご提案をさせていただきます。
▼料金が気になる場合は、料金シミュレーションもお試しください。