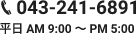医療機関で、患者のカルテを適切に保管・管理することは、診療の質を維持するだけでなく、法令遵守や情報漏洩リスクの低減にも直結します。この記事では、カルテの基本的な整理方法から、安全かつ効率的な保管のポイント、電子カルテ導入時の注意点まで、実践的な知識を詳しく解説します。

書類保管サービス「書庫番人」でコスト削減
カルテ保管の基本
医療機関でのカルテ(診療録)は、患者さんの診療記録が記載された非常に重要な医療書類です。カルテには患者さんのお名前や住所などの基本情報だけでなく、治療歴など多岐にわたる個人情報が含まれています。万が一情報が流出した場合、患者さんのプライバシー侵害という人権問題や医師法違反にも該当します。
知らないと危険!カルテの保管義務
医師法、歯科医師法、健康保険法(療養担当規則)では、カルテの保管期間が明確に定められています。カルテは施術を終了した日から5年間、そのほかの書類は3年間の保存が義務付けられています。
保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。
e-Gov法令検索|保険医療機関及び保険医療養担当規則 第9条
カルテのおおまかな保管方法の種類
カルテの保管方法には、院内スペースを活用した従来型保管法、電子カルテの導入、専門業者の外部倉庫を利用した保管委託の3種類があります。
院内スペースを活用した従来型保管法
最もオーソドックスな方法は、院内のカルテ庫や空きスペースを利用した保管です。電子カルテを導入済みの医療機関でも、過去の紙カルテを院内で保管しているケースが多く見られます。この方法の最大のメリットは、必要な時にすぐにカルテを取り出せることです。特に頻繁に参照する必要のある患者さんのカルテは、院内保管が便利です。
ただし、院内保管ではスペースの確保が最大の課題です。長期間保管していると、カルテ・診療録や処方箋、診療日誌などの書類が増え続け、保管スペースが圧迫されていきます。このため、定期的な整理と法定保存期間を過ぎた書類の適切な廃棄も考えなくてはなりません。
電子カルテの導入
電子カルテの導入には大きく分けて2つの方法があります。紙カルテをスキャンして電子データとして保存する方法と、最初から電子データとしてカルテを作成・保存する方法です。どちらも、物理的なスペースを大幅に節約できるメリットがあります。
ただし、紙カルテのスキャン保存は、単純にPDFとしてスキャンするだけでは原本として認められません。厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」では、電子化した医療情報に「電子署名」と「タイムスタンプ」の付与が義務付けられており、データの改ざん防止と法的証拠能力の確保が必要です。上記のガイドラインに準拠して適切に電子化された場合は、元の紙カルテを廃棄できます。ただし、廃棄する際は、個人情報保護の観点から、専門業者に依頼して安全かつ確実な廃棄をすることが推奨されます。
また、最初から電子データでカルテを作成する方法では、システムを自社開発をしている場合もありますが、電子カルテシステムの導入が一般的です。電子カルテシステムの導入はサーバーは院内設置型とクラウド型から選べます。紙カルテをスキャンしたPDFデータも、多くの電子カルテシステムで管理できます。また、レセプトシステムとの連動も可能なため、業務改善を見込めます。
参考: 厚生労働省|電子カルテシステム等の普及状況の推移
専門業者の外部倉庫を利用した保管委託
カルテの量が院内スペースの限界を超えてしまった場合、専門業者の外部倉庫への委託が有効な選択肢です。かつては医療機関自らが責任を持って保管するのが原則でしたが、厚生労働省が通知を出し、特定条件下での外部保管が認められるようになりました。
厚生労働省|「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正について
この外部委託の一番の魅力は、院内のスペース確保に悩まなくて済む点です。加えて、専門業者は24時間体制のセキュリティ対策を実施しているため、院内保管よりも安全性が向上することも。長い目で見れば、コスト面でも院内保管よりお得な場合が多いです。
紙カルテの具体的な整理・分類方法・ポイント
紙カルテを効率的に管理するためには、適切な整理・分類システムの選択が鍵です。医療機関では一般的にミドルデジット方式、ターミナルデジット方式、氏名カラー方式(50音順)などの分類方法が使われています。
ミドルデジット方式
ミドルデジット方式は、患者番号を桁ごとに分けて整理する手法です。具体的には、中間位桁、頭位桁、末位桁の順番で並べていきます。この方式の特徴は、0〜9の数字にそれぞれ色が割り振られており、100の位と10の位を同じ色の組み合わせにすることで中間位桁がまとまる点です。カルテを探す際はまず該当する色の組み合わせを見つけ、次に頭位桁、末位桁の順に確認していきます。レセコンとの連動も可能なため、番号順に管理したい医療機関に向いています。
ターミナルデジット方式
ターミナルデジット方式は、カルテファイルが10,000枚以上に及ぶ大規模な医療機関に特に適した管理方法です。具体的には、患者番号の1の位と10の位、つまり下2桁に着目し、それらをカラーで区別します。同じ色の組み合わせをまとめることで、末位桁ごとのグループが自然に形成されます。患者番号に飛び番号が存在する場合や、番号の桁数が多い場合にも柔軟に対応できる点が特徴です。また、アクティブ・アンアクティブの仕分けを行えば、よく利用するカルテとあまり利用しないカルテを分けて保管したい場面でも効果を発揮します。
氏名カラー方式(50音順整理)
氏名カラー方式は、患者の氏名をもとにカルテを整理する方法です。日本語の五十音「あかさたなはまやらわ」の各行に、それぞれ専用の色を割り振ります。さらに、1から5までの数字にも色を割り振り、この2つの組み合わせで細かく分類します。背表紙の色をぱっと見ただけで五十音順に並んでいることが分かるため、患者の名前から目的のカルテをすぐに探し出すことができます。また、背表紙には患者名も記載されているため、番号と名前を同時に確認できる点も便利です。
電子カルテ導入の注意点
紙のカルテから電子カルテへ移行したいと考える医療機関も増えています。しかし、電子化には特有の注意点があります。法令対応、コスト管理、セキュリティ対策、スタッフ教育など、多角的な準備が必要です。
電子保存の3原則への対応
電子カルテを導入する際には、厚生労働省が定める「電子保存の3原則」への対応が求められます。この3原則とは、「真正性」「見読性」「保存性」を指します。真正性は、記録の作成者が明確であり、改ざんされていないことを意味します。見読性は、必要なときに問題なく記録を閲覧できる状態を保つことです。保存性は、定められた保存期間中、適切な方法でデータを維持できることです。これらの要件を満たすためには、システムそのものの設計だけでなく、日常の運用ルールをきちんと整備しておくことが不可欠です。
導入・運用コストについて
電子カルテのサービスには、「クラウド型」と「オンプレミス型」という大きく2種類の提供形態があります。それぞれ費用体系が異なるため、導入前にしっかり比較しておきましょう。初期導入費用だけでなく、月額の使用料や保守費用、さらには定期的なシステム更新にかかる費用など、長期的に見て発生するコストも発生します。予算を立てる際には、これらのランニングコストも含めた総合的な視点で検討し、無理のない運用計画を立てましょう。
セキュリティ対策の重要性
患者情報を電子的に管理するため、セキュリティ対策は特に重要です。適切なアクセス権限の設定や、操作履歴を記録するログ管理、システムの定期的な更新など、基本的な対策を徹底しましょう。また、万が一の情報漏洩に備えたリスク管理体制も整えておく必要があります。
スタッフ教育の必要性
電子カルテを導入するにあたっては、システムの整備だけでなく、現場で働くスタッフへの十分な教育も欠かせません。これまで紙カルテを使用していた医療機関では、新しいシステムへの適応に時間がかかることも考えられます。スムーズな移行を実現するためには、あらかじめ十分な研修期間を設け、段階的に新システムへ慣れていける導入計画を立てておきましょう。
電子カルテ導入の具体的ステップ
電子カルテをスムーズに導入するためには、段階的な準備が欠かせません。ここでは、導入に向けた具体的なステップを紹介します。
現状分析と目標設定
「カルテ保管スペースの不足」「検査結果の共有遅延」「処方ミスの低減」など、具体的な問題点を列挙し、電子カルテ導入によって解決したい目標を設定します。この際には、医師、看護師、事務スタッフなどの各部門から意見を集め、課題に優先順位をつけることが大切です。
体制づくりとスケジュール
通常は院長や副院長を導入責任者とし、各部門から代表者を選出してプロジェクトチームを編成します。開業予定の場合は場所が決まってから半年程度、既存医院であれば1年程度の準備期間を見込み、月ごとの進捗目標を設定して計画的に進めましょう。
システム選びと比較
電子カルテには、クラウド型とサーバー設置型の2種類があり、それぞれ特徴やコストが異なります。小規模クリニックでは、月額費用が明確なクラウド型が選ばれることが多い傾向です。複数メーカーから見積もりを取り、初期費用(ハードウェア・ソフトウェア・設置工事)や運用費用(月額利用料・保守料)、追加機能の費用まで細かく比較しましょう。実際の操作画面を体験し、使いやすさを確認することも忘れないでおきましょう。
環境整備と設定
診察室、処置室、受付などにパソコンやプリンターを配置し、安定したWi-Fi環境も整備します。また、診療内容に合わせたマスター設定(薬剤、検査項目、診断名など)や、よく使う処方セットや文書テンプレートの作成も事前に進めておくと、運用開始後の負担を軽減できます。
スタッフ教育と運用テスト
教育の際には、高齢スタッフやパソコン操作が苦手なスタッフには、個別フォローを行う配慮をしましょう。研修後には、実際の診療を想定した運用テストを行い、予約受付から会計まで一連の流れを確認しておきましょう。万が一のトラブル時に備えて、対応手順を明確にしておくことも重要です。
段階的な稼働と改善
一気に全面移行するのではなく、まずは新患のみ、次に再診患者と段階的に移行すると混乱が少なくなります。稼働後1週間はベンダーのサポート担当者の常駐を依頼し、問題点をすぐに解決できる体制を整えましょう。定期的に運用上の問題点を話し合う場を設け、継続的な改善を進めることが長期的な成功につながります。
カルテ保管でお悩みなら書類保管サービスの「書庫番人」にお任せください
「電子カルテの導入が難しい」「紙カルテが圧迫している」などの、カルテの適切な保管と管理でお悩みの医療機関の皆様へ。「書庫番人」の書類保管サービスなら、耐震・耐火性に優れた専用倉庫でカルテを安全に保管します。24時間セキュリティ体制で個人情報を守り、必要な時にはWEB管理システムから簡単に取り出しが可能です。院内スペースの有効活用と管理負担の軽減を実現します。
さらに、保存期間満了後のカルテは、格安の機密文書廃棄サービスもご利用いただけます。個人情報保護に配慮しつつ、カルテ管理の手間とコストを削減し、本来の医療業務に集中できる環境づくりを目指したい方は、ぜひ一度お問い合わせください。