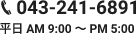「書類の山に埋もれて探し物に時間を取られる」「オフィスのスペースが足りない」「情報漏洩のリスクが不安」こうした悩みは適切な文書管理システムの構築で解決可能です。本記事では、業務効率化、スペース活用、コンプライアンス確保など多角的な視点から文書管理の意義を解説します。さらに、トップダウン式からハイブリッド式まで、自社に合った分類法の選び方や、紙と電子データそれぞれの効果的な管理手法まで、文書管理の基本を網羅的に紹介します。

書類保管サービス「書庫番人」でコスト削減
文書管理の基本とは?
文書管理とは、会社の日々の仕事で作られるさまざまな書類やパソコン内のデータを、必要なときにすぐ取り出せるように整理・保管することです。ただ書類を片付けるだけではなく、会社の大切な情報を有効に使うための重要な業務です。
文書管理には紙だけでなく電子データも含まれます。書類には「作る・使う・保管する・長期保管する・捨てる」というライフサイクルがあります。これらを効果的に行うためには、全体を見据えた仕組みづくりが大事です。人材不足や競争激化が進んでいる現代だからこそ、文書管理の基本をしっかり押さえ、会社全体で取り組むことが成功への近道となります。
文書管理が重要な理由
文書管理が重要な理由を理解することで、企業の生産性向上やリスク軽減につながります。適切な文書管理は時間とスペースの有効活用だけでなく、コンプライアンス強化にも貢献する重要な経営基盤です。
業務時間の有効活用
文書管理の基本ができていないと、1人の社員あたり、1年間で10日分の労働時間を書類探しに費やしているとも言われています。文書管理を徹底すれば、必要な情報にすぐアクセスでき、業務スピードが向上します。また過去の事例やノウハウを簡単に参照できるため、より質の高い意思決定が可能です。部門間の情報共有もスムーズになり、チームワークが活性化します。
オフィススペースの有効活用
紙の書類は日々増え続けるため、定期的な整理・廃棄が必要です。文書管理が不十分だと、保管スペースが拡大し続け、オフィスの有効活用ができなくなります。電子化によるペーパーレス化を図ってもよいでしょう。書類の電子化はスペース削減だけでなく、テレワークなど場所を選ばない働き方も可能にします。これは多くの企業が推進しているデジタル化の第一歩であり、働き方改革にも貢献可能です。管理スペースの削減は、単なる物理的なメリットだけでなく、書類を探す時間の短縮や管理担当者の負担軽減にもつながります。整理整頓されたオフィス環境は、従業員の働きやすさと生産性向上にも寄与します。
リスク管理とコンプライアンスの確保
文書管理はセキュリティ対策と法令順守の両面で重要な役割を果たします。書類の保管場所を明確にし、誰がいつ閲覧したかを記録管理することで、機密情報、個人情報の流出リスクを大幅に軽減可能です。また、業務記録を書類として残しておくことで、トラブルや訴訟発生時に説明責任を果たす証拠となり、社会的ダメージを最小限に抑えられます。取引先とのやり取りを記録した書類が正しく保管されていれば、トラブル発生時の説明根拠となり、企業の信頼維持につながります。適切な文書管理は、企業を情報漏洩や法的リスクから守る重要な防波堤です。
保管期間に注意
文書管理で特に注意すべきなのが保管期間の管理です。書類の種類によって法律で定められた保管期間があり、これに従わないと罰則を受ける場合もあります。会社法、電子帳簿保存法、法人税法など、さまざまな法律によって記載されています。また、就業規則や労働協約など、法律で明確な期間が定められていなくても、永年保管が望ましい書類もあるでしょう。保管期間を守る際には、書類の種類別で法律で定められている最長の保管期間を基準にすると、法的要件を確実に満たしながら管理負担を最小限に抑えられます。廃棄する際には、法定保管期間を守りつつ、廃棄してオフィスをスマートにしていくとよいでしょう。
基本を抑えるためのポイント
文書管理の第一歩は、適切な分類方法を決めることです。どのように書類を整理するかという基本的な方針が明確になっていないと、後々の運用で混乱が生じやすくなります。
ワリツケ式(トップダウン方式)
文書管理者が職務分析をしながら、大分類→中分類→小分類というように上から下へ仕事を細かくグループ化します。「○○の書類は××のファイルに保管する」というルールを定めるのが特徴です。この方式の大きなメリットは、会社全体で一貫した分類体系を構築できることです。そのため、人事異動や組織変更があっても混乱が少なく、長期的な管理に適しています。また、統一性が高いため、全社的な管理が容易になるというメリットもあります。
一方で、経営層や管理部門が考える分類方法が、実際に書類を扱う現場担当者の感覚と異なることは珍しくありません。
この方式を成功させるポイントは、導入時に現場の意見も聞きながら進めることでしょう。トップダウンとはいえ、現場の視点を取り入れることが長期的な運用成功の鍵となります。
ツミアゲ式(ボトムアップ方式)
各部署でルールを決め、現物の書類を確認しながら小分類→中分類→大分類というように下から上へ分類していくのがこの方式です。最大のメリットは、日々書類を扱う担当者にとって使いやすい分類体系になることです。営業部門と経理部門では書類の扱い方が大きく異なるため、それぞれの業務フローに合わせた分類が可能になります。また、現場の実情に合った分類ができるため、導入が比較的容易で現場の抵抗が少ないという特徴もあります。
一方で、部署間で統一性を欠く恐れがあります。全社的な視点での書類検索や管理が難しくなる傾向も見られます。
この方式を効果的に運用するポイントは、定期的な見直しと調整を行うことでしょう。部署ごとの自由度を保ちながらも、最低限の全社ルールを設けることで、バランスの取れた文書管理システムを構築できます。
ハイブリッド式
上記2つを組み合わせた方法で、管理者が大枠の分類ルールを決め、細かい分類は各部署に任せます。全社で統一すべき部分と、現場の裁量に任せる部分をバランスよく設計できるため、多くの企業にオススメの方式です。例えば、法令遵守に関わる重要書類の分類方法は全社統一とし、日常的な業務文書の分類は各部署の判断に委ねるなどの運用が考えられます。この方式を成功させるには、全社共通ルールと部署別ルールの境界を明確にし、定期的な運用状況の確認が欠かせません。多くの中堅・大企業では、このハイブリッド式を採用することで、統一性と柔軟性のバランスを取った文書管理システムを構築しています。文書管理のデジタル化を進める際にも、このアプローチが適していることが多いでしょう。
基本的な分類の具体例
文書管理における効率的な分類方法は、業務の特性に合わせて選択することが重要です。以下では代表的な4つの分類方法とその特徴、適した使用場面を解説します。
業務プロセス別(営業、製造、人事など)
営業、製造、人事などの業務プロセスごとに階層構造を作成します。関連する書類が同じ場所に集まるため、業務の流れに沿った検索が可能です。例えば、営業部門なら「見込客管理→提案→契約→アフターフォロー」などの流れに沿って整理できます。
書類種類別(契約書、見積書など)
契約書、見積書、稟議書、企画書など書類の種類ごとに整理します。同じ種類の書類を一括管理できるため、処理や保管ルールの統一が容易です。発生日や五十音順の副分類を組み合わせると検索性が向上します。電子書類ではメタデータを付与することで多角的な検索が可能になります。
取引先別
営業部門や購買部門で特に有効な分類方法です。特定の取引先に関する全書類を一括管理できます。重要度順、五十音順、業界別などの副分類を設けるとさらに使いやすくなります。取引先ごとのフォルダを設け、その中を時系列や書類の種類で整理するのが一般的です。
作成・発生日別
年→月→日の階層で書類を整理する時系列管理です。いつ作成された書類かが明確な場合に検索が容易になります。法定保管期間の管理や定期的な廃棄処理に適しています。ただし、書類の内容に関する情報がないため、単独での使用は非効率的です。
文書管理の実践方法
効果的な文書管理を実現するには、紙と電子データそれぞれに適した方法を選択することが大切です。状況や目的に応じた最適な管理手法を導入し、継続的に運用することで業務効率化を図りましょう。
紙の管理
紙の書類の管理には、ファイリングが欠かせません。ファイリングの目的は「どこにどのような書類があるかを一目でわかるようにすること」です。紙の管理では、色分けやラベリングを活用して視認性を高め、必要な書類をすぐに見つけられるようにすることが重要です。また、定期的な整理と不要書類の廃棄も欠かせません。
1.バーチカルファイリング
書類をまとめてフォルダに挟み、引き出しやキャビネットで縦に保管する方法です。省スペースで多くの書類を保管できます。
2.バインダーファイリング
バインダーや厚型ファイルに綴じて、本棚などで管理する方法です。背表紙で内容がわかるため、閲覧しやすい特徴があります。
3.ボックスファイリング
書類を挟んだフォルダを、さらにファイルボックスに入れて管理する方法です。分類ごとにまとめやすく、持ち運びにも便利です。
電子データの管理
・ファイルサーバーによる管理
従業員が共通に利用できるサーバー上に電子文書を保管・管理する方法です。
メリット:導入コストが比較的安価です。使い方の教育がほとんど不要です。紙よりも検索時間が短縮され、保管スペースも不要になります。
デメリット:高度な検索機能やアクセス制御機能が限定的です。ファイル名やフォルダ構造に依存するため、規模が大きくなると管理が難しくなります。
・文書管理システムによる管理
専用のシステムを導入して電子文書を総合的に管理する方法です。
メリット:多彩な検索機能で必要な書類をすぐに見つけられます。詳細なアクセス権限設定でセキュリティ強化ができます。バージョン管理機能で書類の履歴を追跡できます。
デメリット:導入・運用コストが比較的高額です。既存の紙の電子化に手間とコストがかかります。利用方法の教育が必要になります。
書類保管サービスに任せる
文書管理の全てを自社で行うのではなく、専門の書類保管サービスを活用する方法もあります。特に大量の紙の書類を扱う企業では有効な選択肢です。
書類保管サービスのメリット
スペースの効率化:大量の紙書類を専用施設で保管することで、オフィススペースを有効活用できます。
セキュリティの向上:温度・湿度管理や防災対策が整った専用施設での保管により、書類の劣化や災害リスクを軽減できるサービスもあります。また、厳格なセキュリティ体制により情報漏洩リスクも最小限に抑えられます。
廃棄作業の効率化:保管期間が終了した書類の適切な廃棄も一貫して行えるサービスを選べば、機密文書の処分に関する手間とリスクを削減できるでしょう。
書類保管サービスを選ぶ際は、セキュリティ体制、料金体系などを比較検討することが重要です。全てのサービスがセキュリティなどの対策をしっかりとしているわけではないため、見極める必要があります。
日々溜まっていく書類は書類保管サービスの「書庫番人」に任せてみませんか?
オフィスに溜まり続ける紙の書類管理でお悩みではありませんか。書類保管サービス「書庫番人」なら、そんな悩みを解決します。「書庫番人」では、企業の文書管理のさまざまな課題に対応し、法令に基づいた適切な保管方法を提案し、専門スタッフが管理をサポートします。はじめて利用する方でも安心して任せられるよう、専属のコンシェルジュが最適な書類保管プランを提案します。書類の電子データ化に対応します。もちろん、全て紙のままでもお預かりします。さらに、保管期間を過ぎた書類の適切な廃棄も格安で提供しています。高度なセキュリティ体制と温度・湿度管理が行き届いた専用施設で、大切な書類を守ります。社内の書類管理の課題を解決したい方は「書庫番人」へご相談ください。