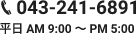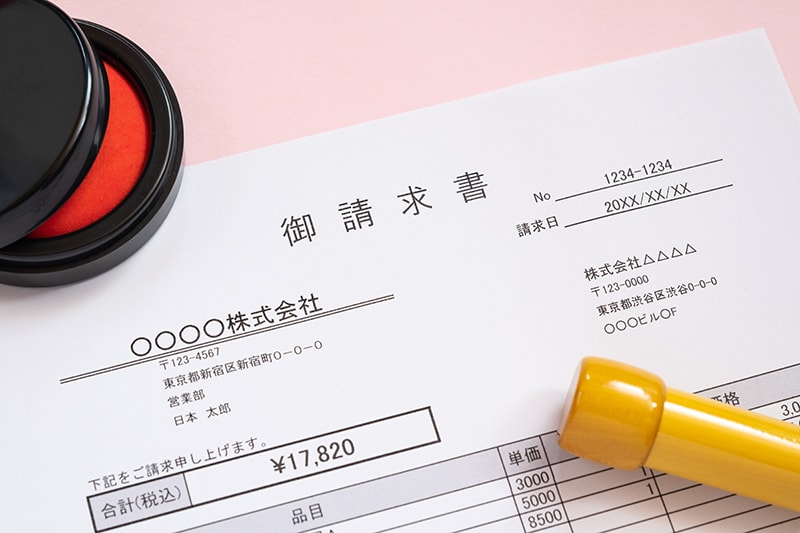請求書管理は、効率的な業務運営と法令遵守に欠かせない重要な作業です。本記事では、請求書を管理する理由やインボイス制度の基礎知識、保管方法の選択肢について解説します。さらに、電子データ化のメリットや課題、書類保管サービスの活用方法も紹介します。

書類保管サービス「書庫番人」でコスト削減
請求書を管理しなければいけない理由
請求書とは、取引先に対して商品やサービスの代金を請求するために提示する書類です。これは、取り引きの証拠となる会計書類の一つに該当します。法律上、請求書を発行する義務はありませんが、確定申告に必要な決算書や申告書の根拠となる重要な書類であるため、適切に管理する必要があります。
また、請求書は会計上重要な書類であるだけでなく、法令を遵守するための観点からも適切に取り扱わなければなりません。書式に関する法律上の決まりはなく、手書きやExcelまたは専用ソフトを使用するなど、形式は自由です。
請求書には以下のような役割があります。
- 取引内容や条件を証明する
- 取引先の未払いを防止する効果
- 税額控除を受けるための証明
- 支払いに関するトラブルを未然に防ぐ
【要チェック】インボイス制度について
2023年10月からインボイス制度が始まり、適格請求書(インボイス)を発行する企業には、その請求書をルールに従って保管する義務が課されました。
インボイスとは、売り手が買い手に対して適用される正確な税率や消費税額を知らせるための書類を指します。税率が複数存在する場合でも、企業が消費税を正確に納められるように、消費税額などを記載した請求書や領収書を基に計算する仕組みです。
インボイスがない取り引きにおける仕入れや経費については、原則として「仕入税額控除」が認められません。ただし、簡易課税制度や2割特例を利用する場合は、インボイスを保管していなくても仕入税額控除を受けることが可能です。
また、請求書に限らず、所定の項目が記載されている書類であれば、領収書や納品書などの名称にかかわらずインボイスとして扱われます。
インボイス制度の記載事項
インボイス制度においては、請求書に以下の事項を記載する必要があります。
- 請求書を受け取る方の氏名または名称
- 売り手(自社)の氏名、名称および登録番号(登録番号は税務署から通知されます)
- 取り引きが行われた年月日
- 取引内容(軽減税率の対象となる品目の場合、その旨を記載します)
- 10%および8%のそれぞれの税率が適用される対価の総額および適用税率
- 10%および8%のそれぞれの消費税額など
さらに、小売業や飲食業、タクシー業などでは、一部の項目を省略した「簡易インボイス」を使用することが認められています。この場合、以下の省略が可能です。
- 宛先の記載を省略することが可能
- 税率または税額のいずれか一方を記載すれば問題はない
請求書の保管期間
保管期間を過ぎる前に請求書を廃棄してしまうと、法律違反となり、税務調査などへの対応が困難になる可能性があります。そのため、保管期限の日付を正確に把握し、それまでは廃棄しないようにしましょう。
法人が請求書を保管する期間は、法人税法に基づき原則として7年間とされています。この期間は、請求書の発行日から計算するのではなく、法人税の確定申告期限の翌日から7年間である点に注意が必要です。
保管期間の数えはじめの例(三月末決算の場合)
法人税の確定申告期限は2ヵ月後の5/31
その翌日の6/1から丸7年保管が必要
また、繰越欠損金(赤字)が発生した事業年度に関しては、請求書を10年間保管する必要があります。このため、請求書は原則として10年間保管するものと考えておくと、トラブルを防ぐことができます。
請求書の管理方法
請求書は、発行者(売り手側)と受領者(買い手側)で管理方法を分けることを推奨します。それぞれの管理に役立つポイントについても紹介します。
自社で発行した請求書の管理方法(売り手側)
自社で発行した請求書については、控えを作成する義務はありません。しかし、入金状況を確認するためにも控えを作成し、保管しておくことを推奨します。特に、適格請求書発行企業が適格請求書(インボイス)を発行した場合には、インボイス制度に基づいて控えを保管する義務があります。
1.未入金・入金済みで分類する
発行した請求書は、入金の状況に応じて「未入金」と「入金済み」に分類することが重要です。
・未入金請求書
請求書を発行したあとは、まず「未入金請求書控え」として保管しましょう。この際、支払い期限順に並べておくと確認がスムーズになります。
・入金済み請求書
入金が確認できた請求書は、「入金済み」と記録した上で、専用のファイルなどに移動してください。さらに、請求書に入金日を記載しておくと、あとの確認作業が容易になります。
2.月ごと・取引先ごとの管理方法
「入金済み」の請求書を整理する際は、以下のいずれかの方法を検討することを推奨します。
・月ごとに管理
入金日を基準に請求書を整理することで、月次決算や資金繰りの管理が効率化されます。
・取引先ごとに管理
取引先別に分類することで、特定の企業との取引状況を迅速に確認できます。取引先が多い場合には、この方法が特に効果的です。
3.支払額の一致を確認する
入金済みの請求書については、支払額が請求額と一致しているか確認することが大切です。この確認を怠ると、誤入金や金額の相違に気づかない可能性があります。
4.紛失防止の工夫をする
請求書を紙で保管する場合は、紛失を防ぐために以下の対策を講じるとよいでしょう。
- ファイルにラベルを付けて内容を一目でわかるようにする
- 紙が飛び出さないよう、適切なファイルやケースを選ぶ
受領した請求書の管理方法(買い手側)
請求書は、受領した企業が支払い状況を確認するための重要な書類であり、適切に保管することが求められます。以下に、効率的な管理方法を解説します。
1.支払い状況で分類する
受領した請求書は、支払い状況に応じて「未払い」と「支払い済み」に分類しましょう。
・未払い請求書の管理
受領後、まず請求内容を確認する前の請求書を「未確認請求書ファイル」に一時保管してください。その後、記載内容が正確であることを確認したら、「未払い請求書ファイル」に移動して管理します。
・支払い済み請求書の管理
支払いが完了した請求書には「支払い済み」と記録し、専用のファイルに保管します。こうした分類により、請求書の混在を防ぎ、状況の把握が容易になります。
2.月ごとや仕入先ごとの分類
支払い済みの請求書は、以下のいずれかの方法で分類すると管理がスムーズになります。
・月ごとに管理
毎月の支出を正確に把握するため、請求書を月別に分類する方法です。特に、定期的な経費管理を重視する場合に有効です。
・仕入先ごとに管理
仕入先ごとに分類することで、特定の取引先との支払履歴を迅速に確認できます。この方法は、複数の仕入先と取り引きがある場合に便利です。
3.記載内容の確認と修正
受領した請求書に記載ミスや不明点がある場合は、速やかに仕入先へ連絡し、訂正や再発行を依頼してください。この対応を迅速に行うことで、後続の支払い業務への影響を最小限に抑えられます。
4.混同を防ぐ工夫
請求書が混在しないよう、以下の工夫を実践してください。
- 支払い済みの請求書にスタンプや印を押し、一目で判別できるようにする
- ファイルやフォルダーに明確なラベルを付ける
「書庫番人」は、請求書の保存に最適な書類保管サービスです。専門のコンシェルジュが法令に沿った安全な保存・廃棄方法を提案し、証明書の発行にも対応します。
電子データでの保管方法
電子帳簿保存法の改正を受けて、請求書を電子データとして保存する企業が増加しています。そこで、電子データでの保管方法についても解説します。
①スキャナ保存
スキャナ保存方式とは、紙で受け取った請求書を電子ファイルに変換して保存する方法です。スキャナーやスマートフォンのアプリなどを活用して請求書をスキャンし、電子データとして保管します。
請求書のスキャナ保存に関する詳細は、国税庁のホームページをご参照ください。
②電子データ保存
電子データ保存方式とは、請求書などがPDFやその他のデジタル形式で発行された場合、そのデータをデジタルのまま保管する方法を指します。この方式は、紙媒体に出力して保管する必要がなく、データのまま保存することで効率的な管理が可能です。特に、2022年からの改正電子帳簿保存法により、電子取引に該当するデータについては電子保管が義務化されています(紙に印刷しての保管は不可)。
電子データ保存の注意点
電子データでやり取りした請求書は、全て電子データのままで保管する必要があります。ただし、単にデータを保存するだけではなく、定められた要件に従って保管することが求められます。この点に十分注意してください。
請求書を紙で受け取った場合は、紙のまま保管することも可能です。また、紙の請求書をスキャンして電子データとして保存する場合、原本の紙は廃棄できます。
改正された電子帳簿保存法では、請求書を電子データとして保管する際に以下の要件を満たすことが義務付けられています。
1.真実性の確保
データの改ざんを防ぐ機能を備えたシステムを導入する必要があります。
2.可視性の確保
保存したデータを簡単に検索・閲覧できるシステムや環境を整えることが求められます。
3.法令遵守
電子帳簿保存法の要件を満たさない方法で保管を行った場合、税務調査時に罰則を受ける可能性があります。
書類保管サービスの活用
請求書を紙や電子データで管理する方法には、それぞれ長所と短所があります。これらの課題を解消する方法の一つとして、書類保管サービスの利用が考えられます。
書類保管サービスは紙の書類を外部の倉庫に保管できるサービスです。「オフィスの書庫が入りきらない」「電子化の導入にはコストがかかりすぎる」そんなときに比較的低コストで書類を保管できます。
・スペースの効率化
大量の紙書類を専用の施設で安全に保管することで、保管スペースを大幅に削減できます。書類保管のためのスペースの賃料よりも書類保管サービスの料金のほうが安い場合はコスト削減に繋がります。
・セキュリティの向上
厳密な管理体制が整備されたサービスを利用すれば、情報漏洩のリスクを最小限に抑えることが可能です。
・廃棄作業の効率化
書類の保管だけでなく、保管期間が終了したあとの廃棄作業も一貫して行えるサービスを選ぶことで、業務の手間を大幅に削減できます。
請求書の管理は「書庫番人」の書類保管サービスに任せてみませんか?
「書庫番人」は、書類管理のプロフェッショナルとして、あらゆるニーズに応えるトータルサポート型の書類保管サービスです。はじめて利用する方でも安心して任せられるよう、専属のコンシェルジュが最適な書類保管プランを提案し、トータルコスト削減、セキュリティ強化、効率的な運用を実現します。さらに、書類保管サービスにとどまらず、不要になった書類の廃棄やデジタル化といった業務にも対応。法定保存文書の期間管理を含むプランニングで、煩雑な書類管理業務を大幅に簡略化します。社内の書類管理における課題を解決したい方は、「書庫番人」を活用してみてはいかがでしょうか。