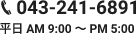ビジネスシーンで日々大量にやり取りされるメールの適切な保管方法や法的要件への対応に、頭を悩ませている企業担当者の方は多いのではないでしょうか。本記事では、仕事メールの正しい保管方法と、法的リスクを未然に防ぐための重要なポイントを、具体的な方法や注意点を交えながら紹介します。

書類保管サービス「書庫番人」でコスト削減
仕事のメールの具体的な保管方法
仕事でやり取りされるメールは、その内容によって法的な取り扱いが異なるため、適切な保管方法が求められます。
電子取引データが含まれるメールの保管方法(電子帳簿保存法関連)
電子帳簿保存法では、電子データでやり取りした取引情報(帳簿類に該当するもの)は、原則として電子データのまま保管することが定められています。
1.電子取引データがメールに添付されている場合
メールにPDF形式の請求書やExcel形式の見積書などが添付されている場合、主に4つの保管方法が考えられます。
方法1:自社で使用しているメールシステムにメール自体を保管する
多くの企業で利用しているメールシステム(自社サーバー運用型、クラウド型など)に、受信・送信したメールを添付ファイルごと保管する方法です。メリットは、メールシステムが、適切な保管機能を有していれば、特別なツール導入や手動作業を省ける点です。
方法2:検索要件を満たしたファイル名をつける
添付ファイルをダウンロードし、電子帳簿保存法の検索要件を満たすファイル名に変更して特定のフォルダやシステムに保管する方法です。
例:「20240515_株式会社サンプル商事_110000.pdf」のように「取引年月日」「取引先名」「取引金額」を含めます。これにより、ファイル名自体が検索キーとなります。シンプルで使い勝手がよいですが、手作業での入力ミスのリスクが伴います。
方法3:事務処理規程を作成して備え付けておく
電子データの訂正や削除のルール、責任者などを明確に定めた「事務処理規程」を社内で作成し、電子帳簿保存法の真実性要件を満たす方法です。この規程を整備し遵守することで、高度なシステムに頼らなくても法令要件をクリアした保管方法が作れます。
国税庁が法人向けの事務処理規程サンプルを公開しています。参考にして自社の実情に合わせて作成するとよいでしょう。
方法4:索引簿を作成して管理する
受領・送信した電子取引データファイルに「連番」を付けて、別途Excelなどで「索引簿」を作って管理する方法です。索引簿には連番のほか「取引年月日」「取引先名」「取引金額」などを記録して、ファイルと関連付けます。ファイル名は単純な連番で済むため、命名ルールで悩まなくてよいのがメリットです。しかし、取引件数が多いと索引簿への入力作業が大変になるかもしれません。
国税庁に、索引簿の作成例も用意されています。
参考:国税庁|索引簿の作成例
2.メール本文に取引情報が直接記載されている場合
添付ファイルではなく、メールの本文に取引情報が直接記載されている場合は、主に以下の2つの保管方法があります。
方法1:自社で使用しているメールシステムにメール自体を保管する
メールを保管できるシステムを使っている場合は、この方法が最も手軽です。ただし、電子帳簿保存法の要件(可視性の確保のためのマニュアル備え付け、検索性の確保など)を満たす必要があります。一般的なメールソフトでは真実性の確保が難しい場合があるため「事務処理規程」の整備と併用するとよいでしょう。さらに、メール本文のどの部分が取引情報に該当するのかを明確にしておくことも大切です。
方法2:メールの内容をPDFなどにエクスポート・変換して保管する
メール本文に記載されている取引情報を、内容を改変することなく、そのままPDFファイルやスクリーンショットなどの形式にエクスポートまたは変換し、電子データとして保管する方法です。利用しているメールシステムが電子帳簿保存法の保存要件(特に訂正削除の防止や履歴確保、検索機能など)を単独で満たせない場合や、保管可能なメールシステムを使っていない場合に有効な手段です。「PDFにエクスポート」という直接的な機能がないメーラーでも、多くの場合、印刷機能からPDF形式で保管できます。保管するPDFなどのファイル名は、「取引年月日」「取引先名」「取引金額」の3項目がわかるように命名しましょう。他には、PDFファイルに連番を付け、別途索引簿を作成して管理する方法もオススメです。この場合、PDFファイル名は連番のみで、索引簿側で取引年月日、取引先、取引金額などの情報を管理するとよいでしょう。
具体的な変換方法としては、メールソフトの印刷機能で出力先を「PDFとして保管」にする方法、スクリーンショットで画像として保管する方法、Adobe Acrobatのような専用アプリケーションを利用して添付ファイルごとPDF化する方法などがあります。
法令に基づくメールの保管義務
企業には法令によってメールの保管が義務付けられています。適切な保管を怠ると法的リスクが生じる可能性があるため、各法令の要件を理解しておきましょう。
電子帳簿保存法
平成10年7月に電子帳簿保存法(電帳法)が施行され、第10条で電子取引の取引情報保存義務が規定されました。電子取引は「取引情報の授受を電磁的方式により行う取引」と定義され、電子メールでのやり取りも含まれます。電子帳簿保存法によると、保管期間は税務申告期限の翌日から7年間です。対象は帳簿類に該当するもののみとなります。
tips 保管期間の特例(10年間保管が必要なケース)
電子帳簿保存法では通常7年間の保管期間ですが、以下の場合は例外的に10年間の保管が必要です。
・青色申告書を提出した事業年度で欠損金額が生じた場合
青色繰越欠損金が発生した事業年度の帳簿書類は10年間保管が義務付けられています。
・青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失欠損金額が生じた場合
災害による損失で欠損金が発生した事業年度の帳簿書類も10年間保管が必要です。
帳簿書類に関する取引情報をメールでやり取りしていた場合、本文に取引情報が記載されているケースでは、メールも同様に10年間保管しなければなりません。添付ファイルにのみ取引情報が記載されている場合には、詳細な取り扱いが明確ではないですが、念のため長期保管しておくことをオススメします。災害や急な経済の冷え込みによる赤字決算は予測できないため、あらかじめ長期保管に対応できる体制を整えておくとよいでしょう。
注意:電子メールで授受した取引データの義務化
2024年1月1日以降、電子帳簿保存法では企業規模や法人・個人事業主にかかわらず、全ての事業者に対して電子取引データの電子保管が義務となっています。
・保管対象となるメールの範囲
EDI、クラウドサービスを介した取引データ、電子メールで送受信した証憑PDF、ホームページからダウンロードしたデータなども含まれます。
・メール本文が保管対象となる条件
メール本文にしか取り引きの証拠がなく「日付、取引先、金額」など、通常証憑に記載される取引情報がメール本文に記載されている場合です。
添付ファイルがある場合はその添付ファイルを、添付ファイルがなくメール本文に取引内容が記載されている場合は、メール本文そのものを保管する必要があります。
関税法
平成24年度関税法改正により、輸出入に関係する取り引きの関係書類を電子メールでやり取りした場合、その電子メールを輸出入許可日の翌日から5年間保管することが義務付けられました。
違反時のリスク
税関のリーフレットでは、故意に電子メールを廃棄して税関の調査を妨げる場合には罰則が課せられる可能性があると書かれています。書類と同じように、電子メールも安易に廃棄しないよう注意しましょう。
電子帳簿保存法が定める電子メール保管の2つの法的要件
電子帳簿保存法に基づいて電子メールなどの電子データを保管するには、2つの適切な要件を満たさなければなりません。
真実性の要件(いずれか1つ以上を満たす)
保管するデータの信頼性と正確性を担保する措置です。
- 取引先からタイムスタンプが付与されたデータを受領する
- 受領後、速やかに自社でタイムスタンプを付与し、実行者・監視者情報を確認できる体制を整える
- データの訂正・削除履歴が確認できるシステムまたは訂正・削除ができないシステムで保管する
- 正当な理由なき訂正・削除を防止する事務処理規程を定め、運用する
可視性の要件(全て満たす必要あり)
保管データを必要なときに確認・出力できる状態にする措置です。
- 保管場所にPC、ディスプレイ、プリンター、操作マニュアルを備え付け、明瞭な状態で速やかに出力できるようにする
- システムの概要書を備え付ける
- 検索機能を確保する
(原則として、「取引年月日・取引金額・取引先」での検索に加え、日付・金額の範囲指定検索、複数項目を組み合わせた検索ができることが求められる)
検索要件の緩和措置
税務調査時にデータのダウンロード要請に応じられる場合、一般事業者は範囲指定検索などが不要です。さらに、基準期間売上高1,000万円以下の小規模事業者は、全ての検索要件が不要です。
要注意!仕事メールの法的保管と見落としがちなポイント
1.法的要件(真実性・可視性)を満たすシステムと運用
メールを含む電子取引データは「真実性」(改ざん防止)と「可視性」(検索・表示)の確保が必須です。訂正・削除履歴が残るシステム導入や事務処理規程の整備が有効です。
2.検索可能な状態と対象メールの明確化
「取引年月日・金額・取引先」での検索が基本です。保管すべきメール(取引情報記載の本文や添付ファイル)の見極めが重要です。
3.電子データは電子のまま保管
メールで受領した電子取引データは電子データのまま保管します。Web上の取引情報はスクリーンショット保管も可能です。
管理の効率化のために「紙で受領・作成した書類は紙のまま保管」「電子データでやり取りした書類(メール含む)は電子データのまま保管」などの区分を基本とするとよいでしょう。紙の書類をスキャナで読み取り電子データとしての保管も可能ですが、その際はe-文書法や電子帳簿保存法のスキャナ保存要件を遵守しなければなりません。
4.法定保存期間の遵守(貿易以外)
一般的な電子取引関連メールの保管期間は法人で原則7年(最長10年)個人で原則5年(最長7年)です。
5.社内ルールの整備と周知
全従業員が正しいメール保管方法を理解できるよう、ルールを明確にし周知徹底することが不可欠です。
6.貿易取引のメール保管の徹底
貿易関係の書類は、原則として全て保管が必要です。貿易取引のメールは「電子取引の取引情報」として税関の事後調査などで厳しくチェックされます。帳簿や輸出許可通知書と同様に、メールにも保管義務があります。スマートフォンアプリなどでメールを管理している場合、自動削除設定やアプリのアップデートにより、過去の重要な取引メールが意図せず消えてしまうリスクがあります。そのため、貿易関連のメールは必ずPCのハードディスクや専用サーバーなど、安全な場所に別途バックアップ・保管する体制を整えましょう。
仕事でのメールの保管方法でお悩みなら書類保管サービスの「書庫番人」にご相談ください
仕事メールの保管方法が複雑で、法的要件を満たせているか不安、そうお考えではありませんか。書類保管サービスの「書庫番人」なら、電子帳簿保存法に対応したメール保管のご相談はもちろん、契約書や経理書類などの機密文書の安全な保管もまとめてサポートします。専門のコンシェルジュによって、お客様の書類管理のお悩みを解決し、業務効率化とコスト最適化を実現します。まずはお気軽にご相談ください。