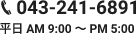近年、企業や団体を狙った情報漏洩やサイバー攻撃のニュースが後を絶ちません。大手企業だけでなく、中小企業や個人事業主にまでその被害は広がり、「うちは狙われるような情報はないから大丈夫」といった考えが通用しない時代になってきました。
この記事では、「情報セキュリティ」とは何かをわかりやすく解説しつつ、企業が取り組むべき具体的な対策についても紹介していきます。専門的な知識がなくても理解できるよう噛み砕いてご説明しますので、ぜひご一読ください。

書類保管サービス「書庫番人」でコスト削減
情報セキュリティ対策とは
情報セキュリティ対策とは、企業が持つ大切な情報資産を、さまざまな脅威から守るための一連の活動を指します。まず整理しておきたいのが、「守るべきもの」「想定されるセキュリティリスク」「守り方」という3つの視点です。まずは扱う情報資産をチェックしてから対策を立てましょう。
企業の情報資産の例
- 顧客・社員の名前や連絡先などの個人情報
- 社内で共有される業務マニュアルや設計書
- 売上データ、契約書、取引先リストなどの機密情報
想定されるセキュリティリスク
情報セキュリティの脅威は日々進化しており、企業はその影響を受けやすくなっています。特に、社内ネットワークに侵入され、社員のコンピューターやサーバーから機密情報を抜き取られるという被害は深刻です。このような被害は、金銭的損失だけでなく、企業としての信用を大きく損なう危険性があります。
また近年では、「サプライチェーン攻撃」と呼ばれる手法が増えています。これは、セキュリティ体制が比較的脆弱な中小企業や下請け企業を足がかりにして、取引先である大手企業のネットワークへ侵入するというものです。
企業が直面するセキュリティリスクの例を、外部リスクと内部リスクに分けて紹介します。
外部リスク(外部からの攻撃)
- ウイルスやマルウェアによる感染
- サーバー経由での不正アクセス
- 外部からのオフィス侵入による情報の持ち出し
内部リスク(企業内の事故や不正)
- 社員がウイルス付きのメールを開いてしまう
- パスワード管理の不備
- カフェなど公共の場で機密情報を扱う
- ノートパソコンやUSBメモリの紛失・盗難
- 故意に情報を流出させる内部不正
これらのリスクはすべて、日常業務の中で起こりうるものです。しかし、適切なセキュリティ対策を施すことで、こうしたリスクを大幅に減らすことができます。
また、事前に被害を想定し、万が一の事故が起こっても事業を継続できるような体制を整えておくことで、損害や信用失墜を最小限に抑えることが可能になります。これは「事業継続計画(BCP)」の観点でも非常に重要です。
企業ができる具体的な情報セキュリティ対策
情報セキュリティを守るには、適切な情報セキュリティ対策が必要になります。また、対策を講じるだけでなく、常に見直さなければ形骸化してしまう点にも注意が必要です。
ここでは、代表的な情報セキュリティ対策を紹介していきます。
技術的対策
まずは設備やシステム面の強化です。導入や設定を誤ると効果が薄れるため、コンサルタントなどプロの手を借りることも検討した方がよいでしょう。
UTM(統合脅威管理)の導入
UTMは、複数のセキュリティ対策をひとつにまとめて管理できる装置や仕組みのことを指します。ファイアウォール、ウイルス対策、侵入の検知と防御、迷惑メール対策、ウェブサイトのアクセス制限、不審な通信の遮断など、さまざまな機能をまとめて提供します。
オフィスのネットワークを守るうえで基本的な設備として広く使われており、設定や管理が一本化されている分、運用もしやすいという利点があります。ただし、UTMだけですべてのリスクに対応できるわけではなく、別の対策との組み合わせも必要です。
VPNの活用
VPN(Virtual Private Network)とは、インターネット上に安全な通信のトンネルを作る技術です。第三者に通信内容を盗み見られたり改ざんされたりしないように、データを暗号化して送受信します。社外から社内ネットワークに接続する際の通信を暗号化し、盗聴や改ざんを防ぎます。
EDRの導入
EDR(Endpoint Detection and Response)とは、パソコンやサーバーなどの端末(エンドポイント)を監視し、異常な動きがあれば検知・対処するセキュリティ対策技術です。各社員が使うPCやサーバーの挙動を常時監視し、不審な動きがあれば管理者に通知します。たとえば、ウイルス感染の兆候を検知して、必要に応じて自動で隔離・遮断し、被害の拡大を防ぐといった対応が可能になります。
バックアップ
感染を防ぐ対策だけでなく、実際に被害を受けたときに復旧できる体制を整えることも大切です。異なる媒体や複数の場所に分けてデータを保存するのは基本的な対策ですが、最近はその保存先を狙った攻撃も増えています。
こうしたリスクに備える方法として、バックアップ専用の機器を使うという選択肢があります。たとえば、バックアップアプライアンスであれば、パソコンやサーバー側から直接アクセスできない構造になっており、保存した情報が攻撃の対象になりにくいという利点があります。
組織的対策
次に、会社としての「ルールづくり」と「チェック体制」の面からの対策方法を紹介します。社内に情報セキュリティ対策を担当する課をつくり、フローなどを整備していく必要があります。
セキュリティポリシーの策定と定期的な見直し
情報の取り扱いルールや、トラブル発生時の対応フローなどを明文化します。また、ルールは放置していればすぐに形骸化します。セキュリティ状況を定期的にチェックし、必要に応じて改善することが大切です。
セキュリティ教育の実施
情報セキュリティ対策の進化のサイクルはとても早いため、新入社員だけでなく、全社員を対象にした定期的な研修が必要です。
定期的な監査や点検
役職に関係なくローテーションで監査を行うなど、透明性ある仕組みを整えると。また、外部の専門機関によるセキュリティ診断も有効です。
情報セキュリティ対策の導入手順
情報セキュリティ対策は、自社の現状を正しく把握し、計画的に進めることが重要です。以下のようなステップを踏むことで、無理なく効果的な対策を講じることができます。
1. 情報資産とリスクの棚卸し
まずは、自社がどのような情報資産を保有しているのかを明確にします。顧客情報、社員データ、営業資料、契約書、開発データなど、機密性の高い情報がどれだけあるのかを把握します。
2. 問題の想定と影響の評価
次に、起こり得る問題を具体的に想定します。たとえば「営業資料が社外に漏れたら」「顧客データが消失したら」といった事態を仮定し、それが業務や信用に与える影響を評価します。
3. 対策の優先順位付け
リスクの高いものから順に、対策を講じていきます。被害の規模や発生の可能性を基準にして、取りかかるべき対策の優先順位を決めましょう。次に、取りかかりやすい対策や低コストでできる改善に着手することで、全体の底上げが可能になります。
4. 計画的な実施
優先順位に従い、実行可能なスケジュールを立てて対策を実施していきます。関係部署や担当者を明確にし、実行体制を整えることもポイントです。
5. 実施後の定期的な見直しと更新
技術も脅威も日々変化するため、定期的な点検や見直しを行い、必要に応じてルールや設備のアップデートは欠かせません。
よくある失敗例とその回避策
情報セキュリティ対策を導入しても、「導入しただけ」で満足してしまうケースは少なくありません。形だけの対策では、実際の被害は防げず、むしろ「対策済み」という過信がリスクを高めてしまうこともあります。以下に、よくある失敗例とその回避策を紹介します。
形だけの対策に終わってしまう
セキュリティポリシーを作成しても、現場に浸透していない、運用されていないケースがあります。なぜこの対策が必要なのか、どう活用すべきかが理解されていない場合、現場では「面倒なルール」として扱われ、形骸化します。
回避策: 導入時に目的と意義を丁寧に説明し、現場からのフィードバックも取り入れて、実情に合ったルールに調整することが求められます。
見直し・更新がされていない
最初に導入した内容を何年もそのまま放置していると、新たな脅威に対応できません。セキュリティ環境は日々変化しており、対応が遅れることで脆弱性が放置されてしまいます。
回避策:半年〜1年に一度は、セキュリティ体制の点検と更新を行うスケジュールを設定します。責任者もしっかり設定します。
BCP(事業継続計画)への対策が不十分
セキュリティを破られないための対策をしても、セキュリティが破られたあとのフローや対策が不十分なことがあります。
回避策: 攻撃を受けたあとの初動対応や、情報復旧の体制も含めて準備しておく必要があります。
まとめ
サイバー攻撃や情報漏洩のリスクが高まる今、情報セキュリティ対策は「あると安心」ではなく「なければ危険」なものになっています。もはや企業にとって、取り組まないという選択肢はありません。
専門知識が不足していたり、社内リソースが限られている場合には、コンサルタントの力を借りるのも有効な手段です。費用がかかるとしても、重大な事故が起きた場合の損害に比べれば、「先に投資しておいてよかった」と思えるはずです。
情報セキュリティは「対策したら終わり」ではなく、「継続して守り続けること」が問われる領域です。できるところから着実に始め、定期的に見直すことが大切です。
紙の書類が多く残っている場合には、書類保管サービスがオススメ
書類保管サービスとは、セキュリティ対策された外部倉庫に紙の書類を預けるサービスです。社内の保管スペースやそのセキュリティ対策の手間が不要になります。電子化と異なり、サイバーリスクの心配も少なく、コストや手間の面でも現実的な選択肢です。さらに、保管期間が過ぎた書類は廃棄依頼するだけで済むため、無駄な保管料も発生しません。
まずは書類保管サービスとはなにかチェックしてみませんか?