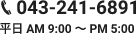デジタル化が進む現代において、企業の書類管理方法も変わりつつあります。しかし、全ての書類をデジタル化できるわけではありません。法的な理由から物理的な形で保管が必要な書類も存在します。この記事では、電子化できない書類の種類と、それらの書類がなぜデジタル化できないのかを明らかにし、効果的な保管方法を解説します。法的要件を遵守しながら、どのようにして書類を安全に保管できるか、企業の書類管理担当者にとって必読の情報を提供します。法的要件を守りつつ、書類を安全に保管する最適な方法を見つけましょう。

書類保管サービス「書庫番人」でコスト削減
電子化できない書類は?
最近の企業活動において、書類の電子化が急速に進んでいます。例えば、契約書や会議の議事録など、多くの書類がデジタル形式で保管されるようになりました。しかし、全ての書類をデジタル化できるわけではありません。法的な規制により、いまだに紙の形で保管しなければならない書類もあります。これは、法的な効力を保証し、特定の情報の機密性を守るためです。中でも、重要な商取引や法的手続きに関連する書類は、その正確性と有効性を保つために、書面での保管が求められることが多いです。今の時代、企業にはデジタルとアナログのバランスを適切に取ることが新たな課題として求められているでしょう。
書面での作成が必須の書類
日本の現行法では、一部の書類を紙で作成することが求められています。これには、宅地建物取引業法に基づく不動産売買や交換の媒介契約書、定期借地契約書などが含まれます。これらの書類は、契約当事者間の明確な合意形成と法的保護を図るため、物理的な書面での取り扱いが義務付けられています。不動産の売買や土地の利用権設定など、大規模な取り引きや権利の移転を伴う契約において、内容の正確性と法的な有効性を保証するためです。紙の書類を使用することで、契約の内容が明確になり、将来的な問題を避けられます。
▼書面での作成が必要とされる書類一覧
| 書類の種類 | 法令 | 理由 |
|---|---|---|
| 事業用借地権設定契約書 | 借地借家法第二十三条第三項 | 公正証書による作成が必要で、紙の形でしか作成できない |
| 農地の賃貸借契約書 | 農地法第二十一条 | 法的な要件を満たす書面が必須 |
| 任意後見契約 | 任意後見契約に関する法律三条 | 公正証書が必要で、電子形式での作成・保管が現在は不可能 |
スキャナ保存の条件が特殊な書類
財務関連の一部の書類は通常、紙の書類をスキャンすることはできません。ただしはじめから電子データとして作成することは可能です。紙の書類へのスキャンが禁止な理由は、財務記録の正確性と完全性を保つためです。技術が進化し、法規制が見直されれば、将来的にはより多くの書類が簡単に電子化が可能になるかもしれません。現在では以上の点から、財務関連書類の多くははじめからデジタル形式で作成されることが一般的になっています。間違えやすい点のためしっかり覚えておきましょう。
▼紙の状態から電子データ化ができない書類一覧
| 大まかな書類の分類 | 細かい書類の種類 |
|---|---|
| 帳簿 | 仕訳帳・総勘定元帳・一定の取り引きの関して作成されたその他の帳簿 |
| 計算、整理または決算関係書類 | 棚卸表・貸借対照表・損益計算書・計算・整理または決算に関して作成されたその他の関係書類 |
以前は電子化できなかったが、今は可能になった書類
技術の進歩と法改正の結果、かつては電子化が許されなかった多くの書類が、今ではデジタル形式での管理ができるようになりました。例えば、労働条件通知書や保証契約書などは、過去には紙の書面での提出が必要でしたが、現在ではデジタルフォーマットでの提出が認められています。これは法改正により、電子的記録でも法的効力を持つとされたためです。同様に、不動産関連の書類もデジタル管理が進んでおり、特定の条件下での電子署名やデジタル形式での保管が可能になりました。
電子化のメリットは、紙の書類に関連するコストの削減、情報アクセスの迅速化、そして環境負荷の軽減に貢献していることです。また、書類のデジタル化は、リモートワークの普及とともに、企業の運営においてさらに重要な要素となっていくでしょう。
デジタル化が進む中で、電子化が可能になった書類は数多くあるため、ここでは特に以前は電子化が認められていなかったものの中から、現在電子化が許可されている書類を紹介します。
▼既に電子化が解禁されている代表的な書類
| 書類の種類 | 法令 | 補足 |
|---|---|---|
| 保証契約書 | 民法第446条 | 法改正により、電子的記録(PDFなど)でも法的効力を所持 |
| 定期借地契約書 | 借地借家法 | 契約書のデジタル管理が可能に、相手方の承諾が必要 |
| 定期建物賃貸借契約書 | 借地借家法 | 電子署名等の使用が認められ、運用が簡略化 |
| 宅建業法35条書面(重要事項説明書) | 宅建業法 | デジタル改革の流れにより、デジタルでの取り引きが可能 |
| 労働条件通知書 | 労働基準法 | 労働者の承諾を得た上でデジタルでの保管が許可されている |
| 特定商取引に関する契約書面 | 特定商取引法 | 法改正により、消費者の承諾を得て電子化することが可能 |
電子化の適用範囲や方法は、契約や取り引きの性質によって異なるため、関連する法令や規定を正確に理解し、適切な手続きを踏みながら実施しましょう。
書類の電子化に関わる主要な法律
書類のデジタル化には、複数の法律が関与しています。これらの法律は、電子化を安全かつ効果的に管理するためには、非常に重要になってきます。これらの法律の内容と適用範囲をしっかりと理解しておきましょう。
電子帳簿保存法
電子帳簿保存法は、国税関連の書類を電子化して保管する際に必要な法律です。この法律は、電子記録の法的効力を保持し、企業がデジタル形式で会計書類を安全に管理するための重要な基盤となっています。特に、書類の「真実性」と「可視性」を確保するための明確な規定が設けられています。書類の「真実性」とはその信頼性を、また「可視性」とはアクセスの容易性を保証するための規定です。
「真実性」を保証するためには、一般的に電子署名や認定タイムスタンプが使用されます。電子署名は書類の正当性を示し、タイムスタンプはその書類が特定の時点で存在していたことを示します。さらに、書類が修正や削除された場合も、その記録が残るため、あとからの確認が容易になります。これにより、書類の変更履歴が透明に保たれ、法的な証拠としての信頼性が高まるでしょう。
一方で、「可視性」の向上も重視されています。これは、契約の詳細やその他重要な情報が必要なときに、すぐにアクセスできるようにするためです。電子帳簿保存法では、書類がディスプレイや印刷によって明瞭に表示され、重要な取り引きの詳細(年月日や勘定科目、金額など)がすぐに検索できるようなシステムの構築が求められています。
これらの規定を遵守することで、企業は会計情報を正確かつ効率的に管理でき、税務調査などの際にもスムーズに対応が可能です。
e-文書法
e-文書法は、企業が保管する必要がある書類を電子化する際の規則を定めた法律です。この法律には、電子書類が紙の書類と同等に信頼されるようにするための複数の技術要件が含まれています。これらの技術要件は、「読みやすさ」「検索しやすさ」「完全性」「機密性」という4つの主要な点に焦点を置いています。
e-文書法の主な4つの技術要件を表にまとめてみました。それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。
| 技術要件 | 補足 |
|---|---|
| 見読性の確保 | 電子化された書類はいつでも明確に表示されるように保管これにより、必要なときの迅速なアクセスと出力が可能になる |
| 検索性の向上 | 必要に応じて素早く検索できるよう、適切なシステムが用意されているこれにより、効率的な情報の取り出しが可能になる |
| 完全性の維持 | データの完全性を保つため、改ざんや消去が行われた場合の記録を残すことが求められるこれにより、書類の信頼性が保たれる |
| 機密性の強化 | データへの不正アクセスを防ぐためのセキュリティ対策が施されているこれにより、機密情報の漏洩リスクが低減される |
電子化できない書類は書類保管サービスに預けるのがオススメ
現在では多くの企業が書類を電子で管理していますが、法的な理由により、紙での形で保管しなければならない書類もまだ多く残っています。そのような電子化できない書類を効率的に管理するためには、専門の書類保管サービスを利用してみましょう。書類保管サービスに任せれば、大事な書類を安全に保護しつつ、オフィス内のスペースも節約できます。さらに書類の整理や検索など、日常的な管理作業もプロの手に任せられるため、社内のリソースをより重要な業務に集中させられるでしょう。また、法的要件に適合する形で書類を保管するため、いつでも法的な問題なく書類を取り出せます。法的なことにかける時間が削減され、ビジネスの進行がスムーズになり、効率的に書類管理もできるでしょう。
電子化できない書類も安心!「書庫番人」に管理を任せてみませんか?
書類の電子化は多くの企業にメリットをもたらしますが、全ての書類をデジタル化することはできません。特に電子化できない書類の整理、保管、さらには廃棄まで、専門的な知識と手間が必要とされます。しかし、書類保管サービスの「書庫番人」では、電子化できない書類だけでなく、全ての書類の管理から廃棄までを、あらゆるニーズに応えトータルでサポートします。電子化できない書類を安全に保管し、管理の手間を省きたい場合には、「書庫番人」が理想的な解決策を提供します。信頼と実績のある「書庫番人」にぜひお任せください。
こちらから気軽にご相談ください。